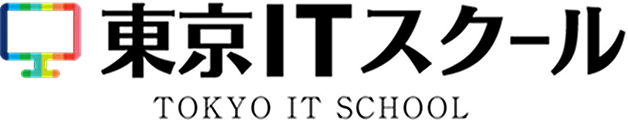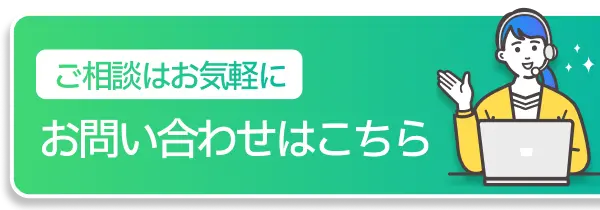株式会社ソルコム様は、元エンジニアの代表が、2000年に設立。BtoBシステムに特化した数多くの実績とノウハウを活かして、システム開発から運用保守、インフラ設計構築まで、幅広いサービスを提供している。
若手の採用を加速させたときに、モチベーションコントロールと育成が必要でした。
御社が教育に力を入れている背景を教えてください。
1つは、社員の年齢構成が20代・40代をボリュームゾーンとしているためかと思ったのですが如何でしょうか。
清水様:若手の採用・育成ともに、実はまだまだこれからの部分が多いのです。全社を通すと20代が多いのですが、東京に限ると20代の社員数は20名前後です。あとは間が抜けて40代の社員になってしまいます。
年齢の構成からも近年は、概ね新人研修は外部に依頼することが中心でした。ここ4、5年は既存社員に対しても、日常的に知識に触れることがないと社員の刺激にもならないと考え、定額制の外部集合研修を取り入れてみました。
しかし、能動的に外部の研修に行くように促しても、積極的に参加する者とそうでない者の二極化が進んでしまいました。新人研修の方は引き続き続けていきながら、今後は教育制度も色々な形で充実させていかなくてはいけないと考え、計画を練って試験運用を始めているところです。
まず教育に関しては、ご満足のいくところまでは引き上げることができていないということですね。
自由度のある教育体制にしてしまうと、能動的に学びにいく方とそうでない方が出てしまい課題が残ったということなのですね。
清水様:そうですね。一方で個人のやる気は活かしてあげたいと思っておりますので、やる気がある人には好きなだけ学ぶことができる環境を作り続けたいと思っています。
一方で、全社員をここまで引き上げると決め、そこまで全社員を引き上げることにコミットせねばとも思っています。コミットラインまでは、マネージャー陣が管理をしていくという体制をとっていきたいと考えています。
代表から「特に若い社員たちの教育をもっとしっかり考えていこう、会社・組織の施策として企画を立てよう」という話も出ました。
代表が直々に若手の育成に重きを置こうとご発言される背景にはどういったものがあったのでしょうか。
清水様:ここ3、4年で急速に若手が増えたということが背景の一つにあります。東京は新卒で入ってきた若者プラス中途で入ってきた中堅以上なのですが、中部は若手採用が上手くいき、ここ2年くらい20代の若手社員が多く入社しています。実は、中部はリファーラル採用が上手くいっています。
リファーラル採用を促進される取り組みを行っていらっしゃるのでしょうか。
清水様:そうですね。全社共通で報奨金制度はありますが、そのために上手く行き始めた、ということではないのです。中部の核となるメンバーが、当社の仕事を楽しい、おもしろいという話をエンジニア仲間に話し、それを聞きつけ即戦力になりうる若手エンジニアが入社を希望し、入社しているのです。
よいスパイラルができはじめていますので、このスパイラルを中部だけではなく全国に広げていくことが今年1年の目標でもあります。
受講した新入社員は現場からの評価がとても高く、質問の内容がプログラマーっぽくなってきたと聞いています。
そういった勢いのある御社で、なぜ新卒採用の研修を弊社にお任せいただけたのでしょうか。
数ある教育会社の中でなぜ弊社なのでしょうか。
清水様:信頼している取引先企業の声は大きかったです。当社が信頼している取引先企業が先に御社のサービスを導入していて、その内容や仕上がりがとてもよかった、と言うのです。
正直なところ、教育会社さんの比較をパンフレットやHPだけで行うことは、とても難しいです。例えば、単発のセミナーなどであれば、モニターとして見学しジャッジすることが可能だと思います。
しかし、2、3カ月という期間の新人研修を全て見学し、ジャッジするということはできません。そこで、重要視しているのが信頼している取引企業から研修機関の導入実績を聞く、口コミを大事にするという方法です。
吉田様:システムシェアードさんは当社と同じSES事業も行われている、ということも大きかったです。御社も新卒社員を迎えられて、その社員を即戦力化するということを行っていると聞いていました。そのため、研修事業を行っている会社さんと比較すると、私たちと同じ立場でもある御社の方が+αがあるのではと考えました。
内部研修から外部研修に切り替えられたタイミングは、御社の中でどのようなお考えがございましたでしょうか。
清水様:モノづくりを如何に近くで見せてあげられるかということに注視した結果です。2012年までは、規模のある受託開発を行っていました。そのときは、Webプログラミングが目の前で繰り広げられていくのを見せることができました。
モノづくりとはどういう工程で進んでいくのか、実際に見せることができていたのです。しかし、受託開発のフェーズは保守に移り変わり、開発工程ではなくなっていってしまった。本来若手社員に見せてあげたい工程ではなくなってしまったのです。そこで、外部にお願いすることに致しました。
よりリアルで実践的な技術に近いところで研修を受けることが1番よいのでは、というご判断であったということでしょうか。
清水様:そうですね。外部研修が終わったタイミングで、先輩社員のいるプロジェクトでOJTを始めることになります。そこではまさしく目の前で開発プロジェクトが展開されているわけです。
そこへの助走として研修期間に学んだことが、開発現場に直結してほしいと考えました。今年の新卒者は3名お世話になりましたが、研修の結果が三者三様でとても面白いものになりました。彼らにとっても刺激が大きかっただろうと思います。
御社は、新卒の方は文理どちらも採用されているかと思うのですが、その3名の方は文理それぞれいらっしゃったのでしょうか。
清水様:そうですね。文系大卒が1名、理系高専卒が1名、理系専門卒が1名でした。理系の2名が圧倒的にプログラミングには慣れていましたが、コミュニケーション能力やものの考え方は文系大卒者の方が一歩アドバンテージとしてありました。
プログラミングがおぼつかない分、考え方とコミュニケーション力でカバーしている。そこに他の2名が刺激を受けていました。こういうこともできるようにならないと、と感じているようでした。三者三様の人材を同時に御社の研修に参加させてとてもよかったと感じています。
その3名の方の現在のご活躍は如何でしょうか。
吉田様:現場からの評価がとても高く、質問の内容がプログラマーっぽくなってきたと聞いています。
清水様:最初は何も分からない状況だったと思うのですが、徐々に「ここが分からない」とピンポイントで状況把握ができるようになっているようです。先輩社員も納得がいく質問ができるようになっているとのことで、頼もしいです。
今年も含め、今後も若手のご採用を進めていくと思うのですが、採用と育成という観点で今後の目標はございますか。
清水様:まず採用に関してですが、新卒者の採用は苦戦しています。新しい採用手法の確立と、これまでのやり方の見直しと強化を図っていきたいと考えています。次に育成についてですが、これまでは外部の研修は新卒しかお願いしていませんでした。
しかし、全ての社員に継続して学びの場を作っていきたいと思っています。そういった意味でも、御社には常に最新の技術を提供するプログラムの作成・提供を期待し、今後もお付き合いを続けていきたいと考えています。