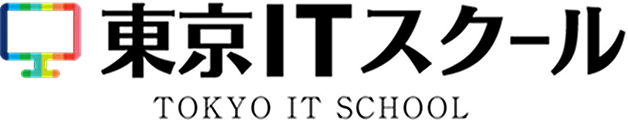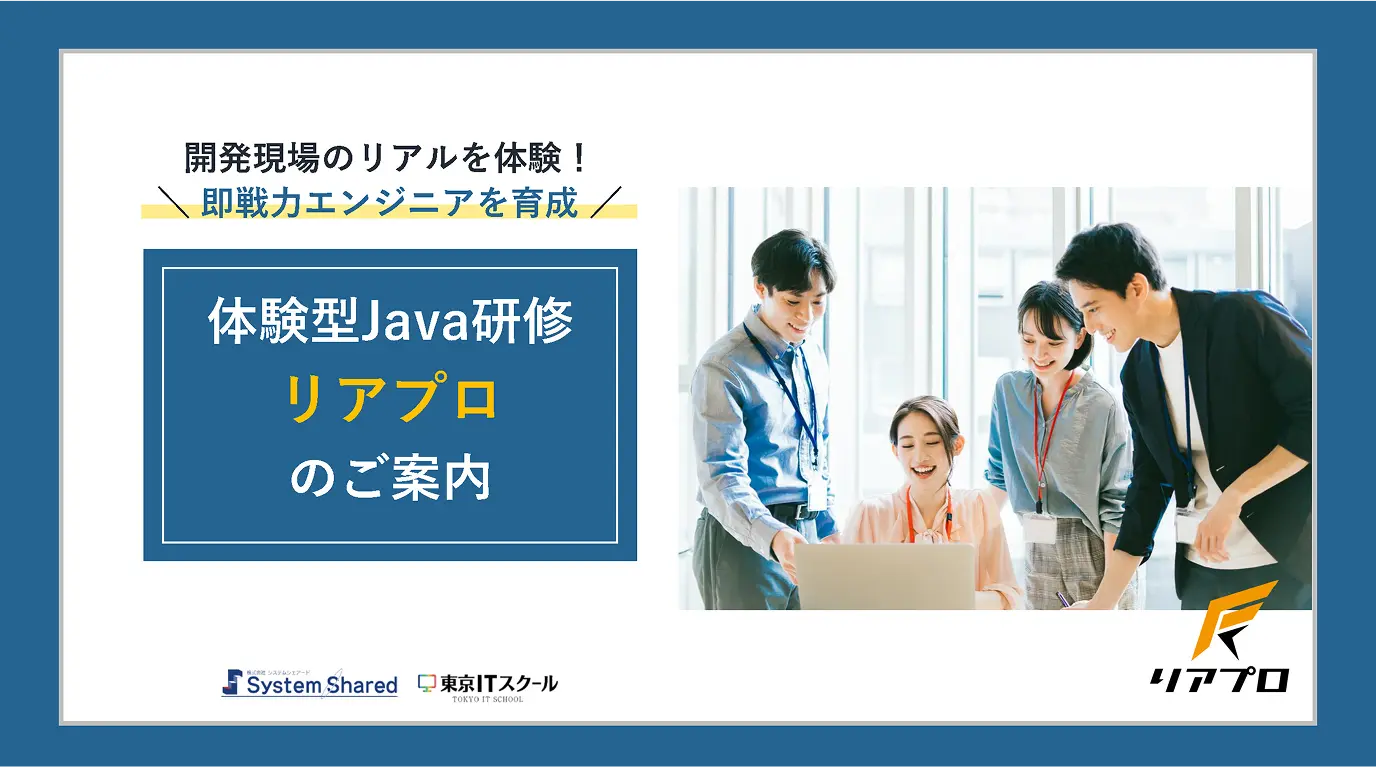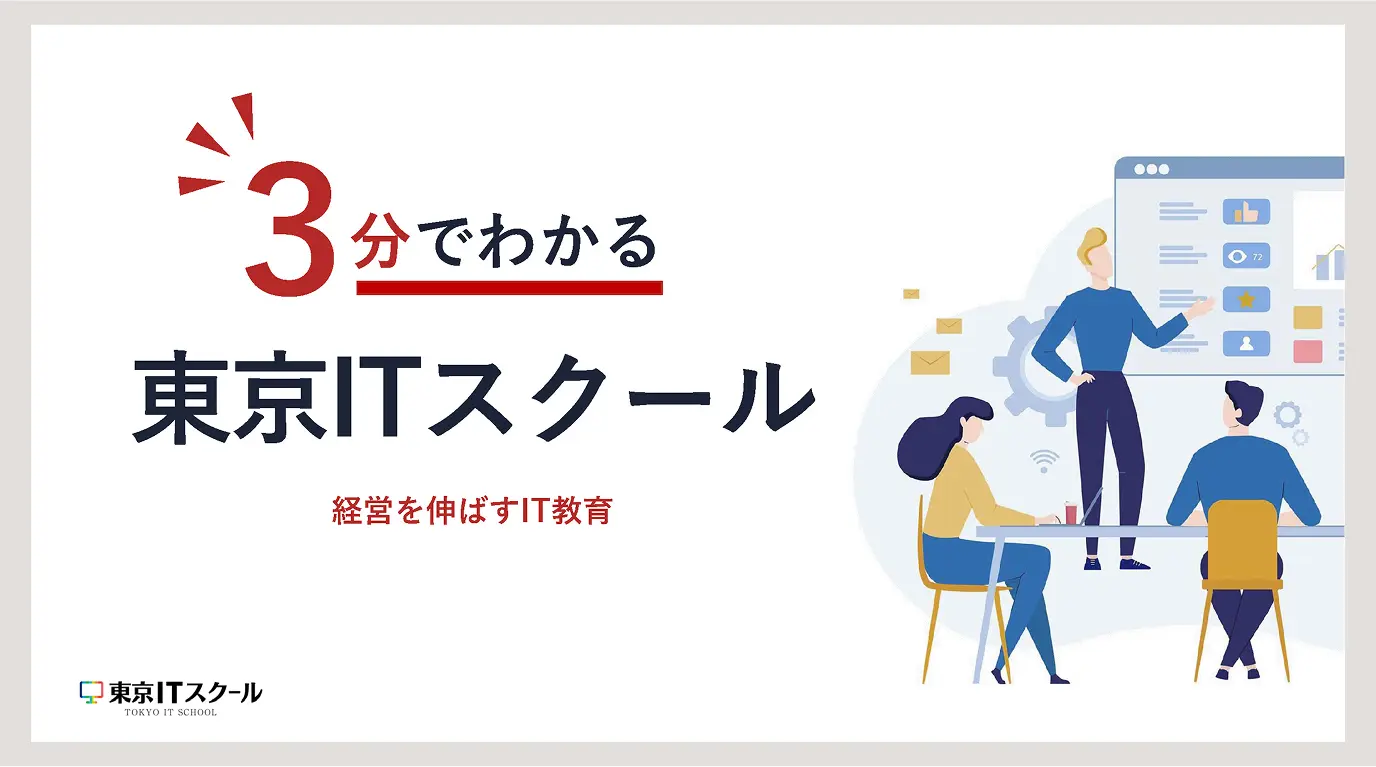メンターとは?導入するメリットやおすすめサービスを紹介

「せっかく業務に必要なスキルや知識を教えたのに、早々に離職されてしまう」
といった課題を抱えている企業は決して少なくありません。時間をかけて業務に必要なスキルや知識を教えて、いろいろなことを任せられるようになったころに辞められてしまうのは、企業にとって大きなマイナスです。
このような課題の背後には、人材育成の際のサポート・フォロー不足があると言われています。スキルや知識を教えることは大切ですが、それだけで人は定着しません。人材を定着させるには、よき理解者と伴走者が必要不可欠です。
そこでおすすめしたいのがメンターの導入です。メンターが適切なサポートやフォローを行えば、人材教育の質が高まるだけでなく、人材も定着しやすくなります。
この記事で、メンターの概要だけでなく導入するメリットや、おすすめのメンターサービスなども紹介しますので、導入を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
メンターとは?OJTやコーチングとの違いは?
まず、メンターの概要とOJTやコーチングとの違いを解説します。
メンターとは?
メンターとは、「助言者」や「相談できる人」と訳され、「メンタリング」と呼ばれる定期的な面談や対話を通じてアドバイスや成長・精神面のサポートを行う人を指します。
メンターは直属の上司ではなくほかの部署の先輩社員が務めるのが一般的です。
メンタリングを受ける人(メンティー)が話しやすいように、年が近い先輩社員をメンターに選ぶ企業が少なくありません。
メンタリングとOJTの違い
メンタリングは、基本的に
・直属の上司ではない先輩社員が
・1対1の対話を通じて
・課題解決のためのアドバイスや精神的なサポートを行う
ものです。
メンターとメンティーの関係性もフラットなため、率直なコミュニケーションができます。
一方、OJTは
・直属の上司や同じ部署の先輩社員が
・実際の業務を通じて、実務に必要なスキルや知識を教える
ため、どちらかというと教育訓練の側面が強いものです。
メンタリングと違い、新入社員と上司・先輩社員の間には上下関係や利害関係があります。そのため、メンタリングに比べて新入社員が委縮してしまいやすく、質問や相談ができなくなることがあります。
メンタリングとコーチングの違い
メンタリングと混同されやすいものには「コーチング」もあります。どちらも1対1の対話を基本にして行われますが、次のような違いがあります。
コーチングは、メンタリングと違い、技術やスキルの習得など実務面での課題解決をサポートする際に用いられる人材育成手法です。対話によって気付きを促し、相談者自らが自発的に課題解決に向けて動けるようサポートします。
一方メンタリングは、コーチングと違ってメンタル面での不安解消やサポートにウェイトが置かれます。業務に関わることだけでなく、プライベートな悩みの解決をサポートすることもあるのが特徴です。
メンタリングでは、必要に応じて専門の相談機関や別な人につなげることも求められます。
メンターを導入すべき理由とメリット
ここからは、メンターを導入すべき理由と導入するメリットを解説します。
メンターを導入すべき理由
メンターを導入すべき理由は、導入すると従業員の満足度が向上し、離職率が低下するからです。
コロナ禍以降、価値観や働き方はますます多様になりました。なかでも顕著なのが「ワークライフ・バランスに対する意識の変化」と「ハラスメント問題」です。
コロナ禍で柔軟な働き方ができるようになった人のなかには「仕事をするために生きるのではなく、もっと人生を楽しみたい」と考える人も増えました。しかし、周りに相談できる人がいない・ロールモデルにしたい人がいないという人も多く、一人で抱え込んだ結果、離職した人も少なくありません。
また、ひと昔前までは、直属の上司は仕事を教えると同時に、プライベートでも付き合いを持つなどして、新入社員のよき理解者・相談役でもありました。
しかし、昨今は仕事を離れてプライベートでも職場の上司と付き合おうとする人はそこまで多くありません。
上司としても、プライベートでも付き合おうとすれば「パワハラ」「セクハラ」と言われてしまいかねない空気があり、業務以外で仲を深めたり信頼を築くのは容易ではないでしょう。
そこで、導入したいのがメンターです。
メンターを導入することで、社員が様々な悩みや不安を気軽に相談できるようになり、働きやすくなります。
導入するメリット①新入社員の早期離職が防げる
せっかく教育しても、新入社員が早期に離職してしまうと悩んでいる企業は決して少なくありません。早期離職の背景には、相談できる人がいない不安や、アドバイスがもらえないことに対する不満があるとされています。
新入社員の悩みは、直属の上司や先輩には相談しにくいものであることが少なくありません。そこで、上司・部下といった立場を超えて相談できる相手がいれば、新入社員の不安や悩みが解消されやすくなるため、早期離職が防げるでしょう。
導入するメリット②メンティーが職場に適応しやすくなる
メンターを導入すると、新入社員が質問や相談をしやすくなります。
メンタリングを通じて職場で良い人間関係が築ければ、新入社員も職場に適応しやすくなり、より効率的に人材育成が進められるでしょう。
導入するメリット③メンタルの支えが得られる
新入社員にとって、新しい職場は期待と不安の入り混じる場所です。慣れないうちは、プレッシャーやストレスも大きいでしょう。
しかし、様々なことを気軽に相談できる相手がいれば、精神的な支えができます。
業務と直接かかわりのない人と、1対1でゆっくり話すことは、ストレスや不安の解消にもつながることは想像に難くありません。
メンターとして育成するのに向いている人の特徴
メンターに向いている人の特徴は次のとおりです。
- 傾聴力(相手の話を聴く力)がある
- コミュニケーション能力が高い
- 責任感がある
- 職場の状況や人間関係をよく知っている
- メンティーと業務上の利害関係がない
傾聴力がある
メンターとして育成する人材を選ぶ場合、まず傾聴力(相手の話を聴く力)があるかどうかをチェックしましょう。
傾聴とは、相手の話を聴いてそれを受け入れることをいいます。ただ話を聴くのではなく「そうなんだね」「あなたはそう思うんだね」と受け入れることも含めて「傾聴」です。
メンタリングをはじめると、どうしても納得できない・受け入れられない話を聴くこともあります。それでも、できるだけ理解しよう・受け入れようという姿勢で話が効ける人はメンターに向いています。
コミュニケーション能力が高い
メンターによるメンタリングは、1対1の対話が基本です。ただ話を聴く・アドバイスをするだけでなく、相手の表情やしぐさ、声のトーンなどから相手の心情を推し量ったり、メンティーが話しやすい雰囲気づくりができる人はメンターに適任です。
上からものを言ったり、高圧的な態度を取ったりせず、フラットな姿勢でメンティーとコミュニケーションが取れる人は、特にメンターに向いています。
責任感がある
責任感があることも重要です。メンターは、メンティーのよき理解者であると同時に伴走者である必要があります。伴走者であるからには、ゴールテープまで共に走り切らなければなりません。
この場合のゴールは、メンティーの成長です。
そのことを理解したうえで、メンティーの困りごとをただ解決するだけでなく、メンティーを成長させることに対して責任を持てる人が適しています。
職場の状況や人間関係をよく知っている
メンタリングの結果、同じ職場の人とメンティーがコミュニケーションを取りやすいようサポートしたり、他の人の手を借りたりする必要が出てくる場合もあります。メンターには、職場の状況や人間関係もしっかり把握してる人を専任しましょう。
表に出ている情報だけでなく、非公式・裏の情報まで把握できていれば、より様々なサポートが行なえるので、情報通や人脈が太い人はメンター向きです。
メンティーと業務上の利害関係がない
メンターは、メンティーを評価したりする立場にない人物である必要があります。
直属の上司や先輩社員は、メンティーを評価する立場の人です。仕事のやり方などを質問する場合は適任かもしれませんが、メンティーは常に「この人に相談したら自分の評価が下がるのではないか」「自分を見る目が変わるのではないか」と思いながら接していることでしょう。
しかし、それでは気兼ねなく様々な相談ができません。
メンターとして育成する人を選ぶ場合は、メンティーを評価したり、メンティーと一緒に仕事をすることが少ない、業務上の利害関係がない人を選んでください。
メンターを育成するには
先輩社員であれば誰でもメンターになれるわけではありません。メンターになるには、前述の傾聴スキルやコミュニケーション能力なども必要になります。
効率的にメンターとなる人材を育成するには、メンター育成研修を実施するのがおすすめです。研修では、メンタリングの基礎知識だけでなく、メンターとしての心構えやアドバイス・サポートのテクニックなども学べます。
しかし、研修を受けたからといって短期間で優れたメンターを育成できるわけではないうえ、それなりに費用もかかる点は頭の片隅に置いておきましょう。
メンターを導入するなら「キャリサポ」がおすすめ!
「すぐにでもメンターを導入したい!」
「もっと気軽にメンターを活用したい!」
という方には、東京ITスクールのエンジニア特化型メンターサービス「キャリサポ」がおすすめです。
経験豊富なメンターが一人ひとりに合わせてサポート!
従業員の満足度を向上させることは「働きやすい・働きたい職場」を作る上で必要不可欠です。しかし、中小企業の経営者や人事責任者が現場のエンジニアと対話をしながら、キャリアパスを構築するのは、難しいと言わざるを得ません。
「キャリサポ」ではSESエンジニア業界に特化したメンターがメンティーと1対1で対話をし、悩み解決や帰属意識の醸成、キャリアパス構築をサポートします。
「キャリサポ」をご利用いただくことでエンジニアの満足度向上だけでなく、経営者や管理職の時間の確保にもつながる点が多くの企業様に喜ばれています。
スキルアップ・キャリアアップに役立つ研修も受けられる!
メンタリングの結果に応じて、東京ITスクールの200以上の研修が受けられるのもキャリサポの魅力です。
毎月新しい研修が追加されるため、第一線で活躍し続けるために必要なトレンド技術も学んでいただけます。
月次レポートでエンジニアの状況が一目瞭然!
「キャリサポ」では、ご利用いただいた方一人ひとりの研修進捗(しんちょく)レポートを作成いたします。
フォローアップ内容や育成計画に合わせてどのようにPDCAを行っているかなど、社員の方の状況がひと目でわかる点が好評です。
レポートは、離職防止に役立つ施策や、エンジニアの成長につながる施策を考える野にも役立ちます。
メンターを導入して人材育成の質を向上させよう!
新入社員の多くは、期待だけではなく大きな不安も抱えています。そのフォロー・サポートの希薄さが、早期離職につながっていることは言うまでもありません。
新入社員の早期離職を防ぎたいなら、メンターによるメンタリングを導入してはいかがでしょうか?
気軽に様々なことを相談できる相手がいて、必要なアドバイスやサポートが受けられる職場なら、新入社員も安心して働けるようになり離職率も低下するでしょう。
メンターを導入してみたい・エンジニアのメンタリングに悩んでいる企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
おすすめの研修・講座はこちら

東京ITスクール 湯浅
現場SEとして活躍する傍ら、IT研修講師として多数のIT未経験人材の育成に貢献。現在は中小企業を中心としたDX、リスキリングを支援。メンターとして個々の特性に合わせたスキルアップもサポートしている。趣味は温泉と神社仏閣巡り。