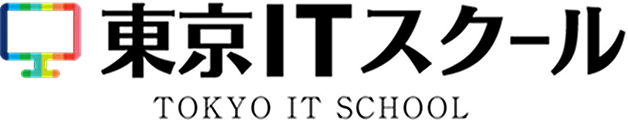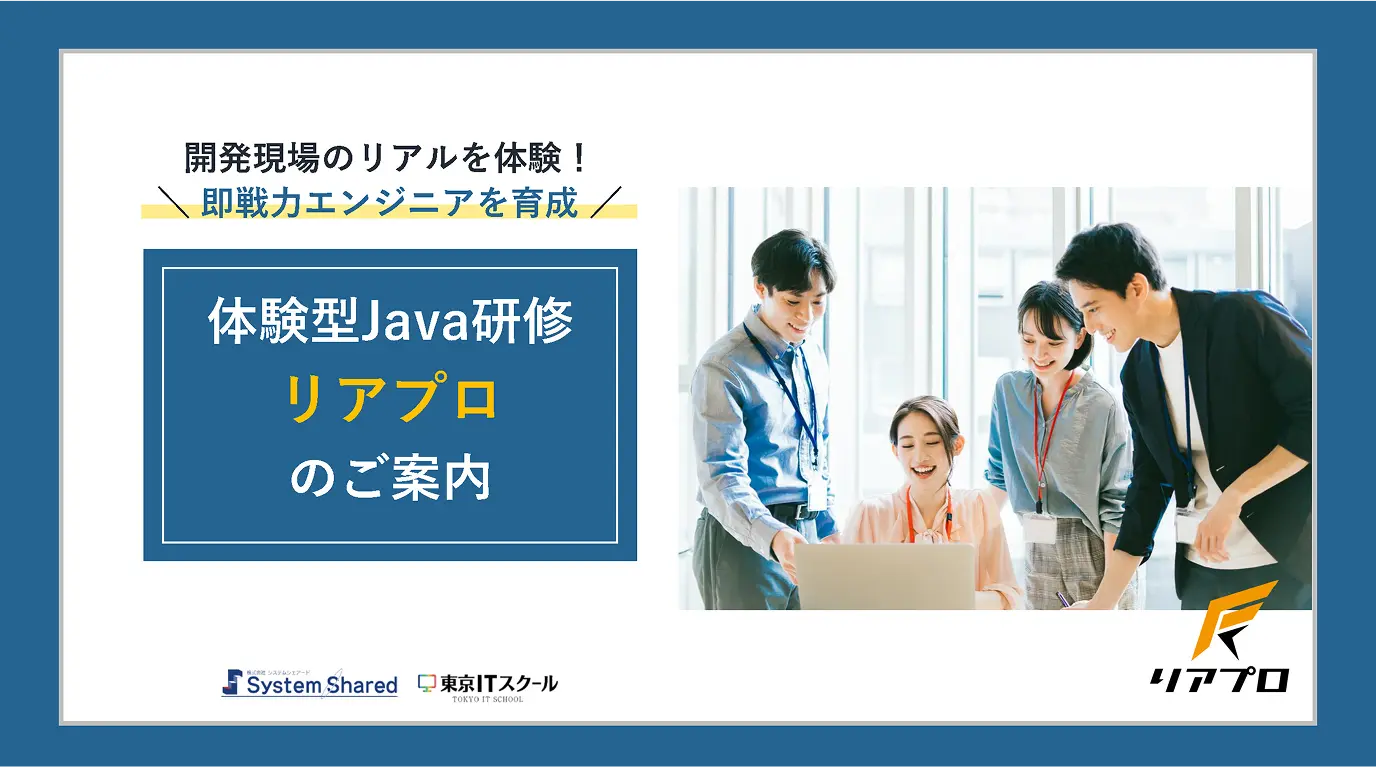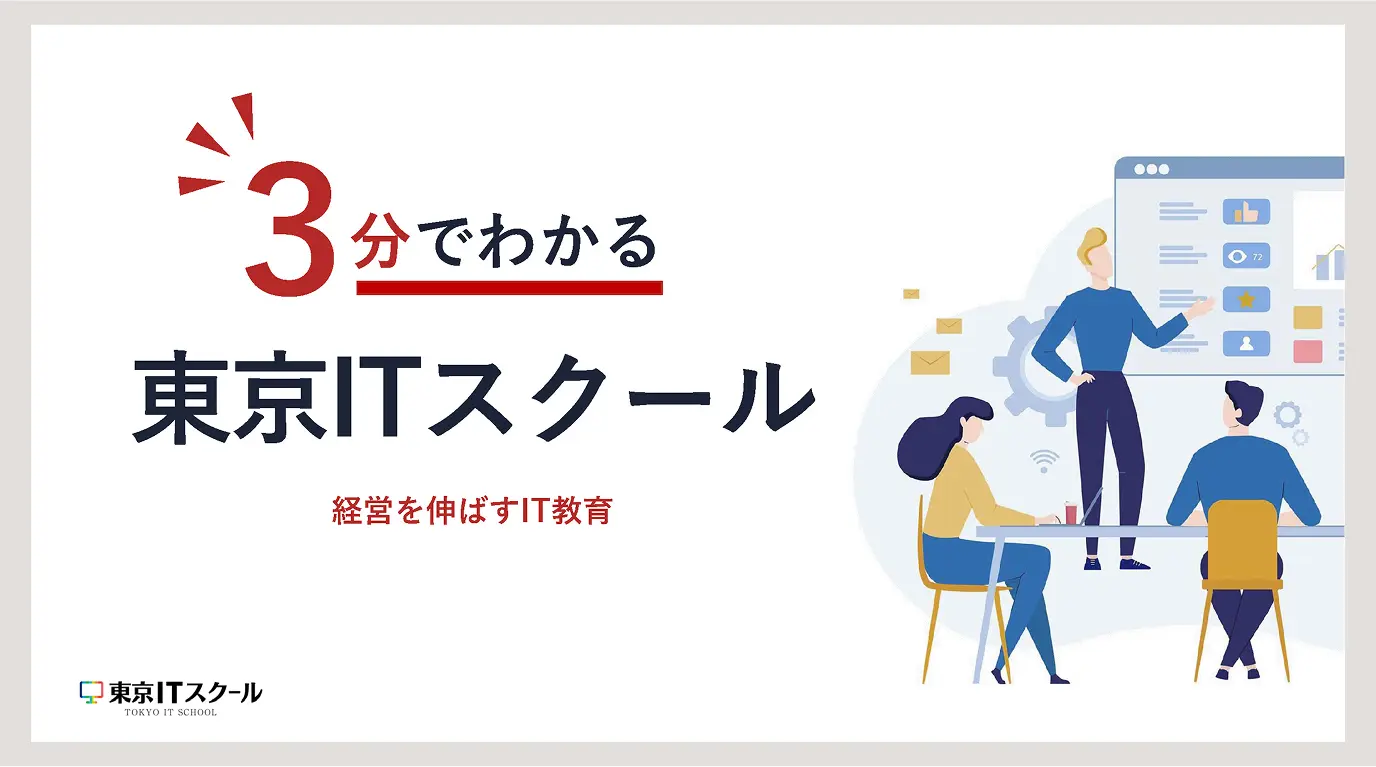研修アンケートの基礎知識とは?実施で理解すべきこと・活用方法

研修のブラッシュアップや改善に大きく役立つのがアンケートです。しかしそのメリットを享受するためには、効果的な方法で行うことが大切です。
この記事では、研修時に行うアンケートについて解説します。
実際にアンケートを行う際の参考になる内容です。担当者の方はぜひご一読ください。
研修アンケートの目的と取り組み
まず、研修アンケートを行う目的について解説します。
目的① 研修内容の理解度を測るため
研修内容の理解度を測るためのアンケートでは、研修が目指すスキルや知識が参加者にしっかりと伝わったかを確認します。
具体的な質問例としては、「研修の内容は、仕事に直結する知識・スキルを学べたか」や「取得したスキルは、現場で活用可能だと感じたか」等があります。また実際の業務に適用させるためのシミュレーションやロールプレイが行われた場合は、「シミュレーションを通じて、学んだ内容を実践する自信がついたか」等の質問も有効です。
理解度を正確に把握するためには、5点評価や二者択一ではなく、詳細な自由回答形式の設定も適宜行いましょう。これにより具体的な反応や感想を得られ、より精緻な理解度の分析と改善策の策定が可能になります。
目的②研修参加者の満足度調査
参加者の満足度調査は、研修が成果を上げているかを評価する一定の指標となります。しかし、単純に参加者がどれだけ研修に満足したかを尋ねるだけでは充分ではありません。
研修内容が参加者の期待と一致していたか、また、期待以上の成果を得ることができたか、も評価する重要な要素です。例えば研修後のアンケートで「研修内容はあなたの期待に応えましたか?」と聞くことで、満足度だけでなく期待とのギャップも測定できます。
それぞれの企業の研修目標に合わせて、最適な質問内容を設定することが求められます。
目的③ 研修の改善点特定
研修アンケートで改善点を特定することで、現状を理解し修正するための重要な指針となります。まず、研修アンケートを通じて、具体的な問題や改善が必要なポイントを見つけることが重要です。記述式の質問や5点リッチャートスケールなどの評価尺度を採用することで、詳細なフィードバックを得られます。
この結果を集計し、悪い評価が集中する項目や参加者からの具体的なコメントを基に改善点を特定します。結果は次回の研修内容改定に活用します。また参加者たちのユニークな視点から新たなアイデアを得て、組織全体の改善に繋げる事例も見られます。
ただし、気をつけるべきは、全ての意見や要望に対応しようとすると研修の目的がぶれてしまうことです。最も重要な改善点は、研修の目的達成に最も寄与するものを優先的に選び出すことが重要です。それに基づき、余裕があれば次点の改善点に取り組む方法で進めていきましょう。
目的④ 次回の研修企画への反映
研修アンケートの成果を次回研修の企画へ真摯に反映することは、企業の人材育成 を成功させる鍵となります。まずは、アンケートの分析結果を全ての関係者と共有することで、問題箇所や改善の余地がある部分を明らかにします。次に、具体的な改善策を策定し、それを研修計画に盛り込むことが重要です。
たとえば、アンケート結果で参加者が特定のセッション内容を理解するのに苦戦していることが判明した場合、そのセッションの内容を見直すか、必要に応じて専門的な講師を招くなどの改善策を検討します。また、参加者の満足度が低かった場合は、研修の形式や進行方法、時間配分などを再評価することも重要です。
具体的な改善策の定義と実行は、研修内容の質を維持し、さらに向上させるために不可欠なステップです。アンケートは単なるフィードバックツールではなく、研修の進化と成熟を促進する強力なリソースであると理解することが重要です。
研修アンケートの設計
研修アンケートの設計は、具体的な改善方針を導き出すための重要なステップです。適切なアンケート設計によって、参加者の声を正確に捉え、未来の研修改善への道筋をつけることが可能となります。
質問項目の設定例
研修アンケートを効果的に設計するためには、質問項目の設定が鍵となります。
研修内容の理解度を測るための質問項目としては、
「この研修で最も印象に残った内容は何ですか?」
「研修で学んだことを実務に活かす自信はありますか?」
などが考えられます。参加者がどの程度研修内容を理解し、実際に活用できるかを把握することができます。
また、参加者の満足度を測るための項目として、
「研修の時間配分は適切でしたか?」や
「講師の説明は分かりやすかったですか?」
といった具体的な項目も設定しましょう。参加者の満足度を測り、研修の質を確認することができます。
自由回答形式で「研修の改善点や今後の期待があれば教えてください」といった質問を含めることも有効です。
これらの質問項目を組み合わせることで、研修の質を向上させるための具体的なデータを得やすくなるでしょう。
アンケートに適した回答形式
効果的な回答形式は質問内容や目的により異なりますが、一般的には選択式質問や5点リッチャートスケールなどがよく使われます。
選択式質問は回答者が既定の選択肢から選ぶ形式で、集計や分析が容易です。一方、リッチャートスケールは質問に対する回答者の同意度や満足度を測るのに適しています。
また、自由回答式も重要であり、回答者が感じたことや提案を自由に書き込むことができます。自由回答式は具体的な改善点を抽出するのに有効ですが、分析が手間取る可能性があります。
適切な回答形式を設定することで、高品質なフィードバックを得られ、効果的な改善策を打ち出すことが可能になります。
研修アンケートの長さと質問数
アンケートの長さと質問数は、適切に設定することが必要です。長すぎるアンケートは回答者の負担になり、短すぎるものは評価が十分でない場合があります。一般的には、5から10問程度の質問が適切とされています。また、質問数が増えるにつれてアンケートの長さも増加します。一つの質問につき1分以内で回答できるよう配慮すると、全体の長さは適切になりやすいです。
ただし、これはあくまで一般的なガイドラインであり、アンケートの目的や参加者の特性により最適な長さや質問数は異なります。
研修アンケートの作り方、実施方法
それでは、実際に研修アンケートの作り方と実施方法についてみていきましょう。
アンケートの作り方:オンラインツールの活用
オンラインアンケートツールの利用は、アンケート実施における効率性と利便性を大いに向上させ、研修の効果測定にも役立ちます。紙ベースのアンケートに比べて入力作業の効率化、集計結果の即時取得、ターゲットへの直接送信などのメリットがあり、事後のフォローアップにも最適です。
代表的なツールとしてはGoogleフォームやSurveyMonkeyなどがあり、研修内容に合わせた質問の設計が可能です。これらはユーザーフレンドリーで視覚的なインターフェースを持ち、独自の質問を簡単に作成でき、設問例を活用することで精度を高めることができます。
また、回答データは自動的に集計され、分析のためのグラフやチャートも生成可能で、研修後の理解度評価に活用できます。
なお、これらのツールを活用する際には、使用者のプライバシーに配慮し適切な情報管理を行う必要があり、セキュリティの強化が求められます。
紙ベースもありだが、オンラインがおすすめ
研修アンケートを実施する際、紙ベースのアンケートも依然として有効な手段です。特に、現場での即時フィードバックが求められる場合には重宝されるでしょう。しかしながら、オンラインでのアンケートを本記事ではおすすめします。
オンラインアンケートは環境への負荷を軽減し、紙資源の節約につながるだけでなく、データの集計や分析が自動化されるため、結果を迅速に処理しやすくなります。
さらに、オンラインプラットフォームを使用することで、回答者は自分の都合に合わせて自由な時間に回答でき、回答率の向上が期待されます。質問の分岐や条件付き表示など、柔軟な設計も可能であり、より質の高いデータを収集することができます。
匿名性が保たれることも、正直なフィードバックを得る上での大きな利点でしょう。セキュリティ面でも、オンラインでのデータ管理は安全性が高く、個人情報の保護に配慮した設計が可能です。
テンプレートの利用
研修アンケートの作成は、テンプレートを利用することで作業効率が大幅に向上します。テンプレートは、あらかじめ設定された質問項目や回答形式を活用することで、アンケートの設計プロセスをスムーズに進める助けになります。
特に、複数の研修を実施する企業にとっては、テンプレートを利用することで一貫性を保ちつつ、迅速にアンケートを作成できるので有用でしょう。
テンプレートには、一般的な質問項目や評価基準が含まれているため、初めてアンケートを作成する担当者でも安心して利用できます。ただし、テンプレートをそのまま使用するのではなく、自社の研修の目的や対象者に合わせてカスタマイズすることが重要です。
特定のスキルの習得度を測るための質問や、研修内容の具体的な改善点を尋ねる自由回答欄を追加することで、より効果的なアンケートを作成できるでしょう。
オンラインツールと組み合わせてテンプレートを利用することで、デジタル化されたアンケートの配布、回収、分析が容易になり、作業時間の短縮に繋がります。これにより、より多くのリソースを分析やフィードバックに充てることが可能となり、研修の質向上に貢献します。テンプレートは時間の節約だけでなく、アンケートの質を高めるための有効な方法でもあるのです。
リマインダーの効果的な利用
リマインダーの効果的な利用は、研修アンケートの回答率を高めるために重要な戦略となります。リマインダーは参加者にアンケート回答の催促をするもので、そのままでは回答しないか忘れてしまう可能性のある人々に対して、再度アンケートに気を付けてもらう効果があります。
重要なのは、リマインダーを適切なタイミングで送り、参加者を困惑させないことです。例えば直後に送ると、参加者は圧迫感を感じるかもしれません。逆に、送るのが遅すぎると、研修アンケートの存在を忘れてしまう可能性があります。リマインダーは通常、研修アンケート配布後1週間程度を目安に送ることが一般的です。
また、リマインダーの内容も重要です。ただ単に「アンケートの回答をお願いします」とするだけでなく、アンケートの目的や、それがどのような改善につながるのかを参加者に伝えて、回答の意義を理解させ、回答への動機付けを促すことが有効です。
このような取り組みを行うことで、アンケートの回答率と質を向上させ、より有意義な結果を得ることができます。
研修アンケート結果の分析
アンケート結果の分析は、研修の効果を評価し改善策を導き出す大切なステップです。分析は以下のような内容に分けることができます。
・統計データの活用
・自由回答の分析方法
・結果の可視化
それぞれについて確認していきます。
統計データの活用
アンケート結果から得られる統計データは研修の効果測定に欠かせません。次のステップへ進む前に十分な分析が必要となります。統計データから研修内容の理解度や満足度、改善点を数値化し、具体的な数字で見ることができます。
例えば、研修後のアンケートから得られた統計データを用いて、研修プログラムの進行状況を定期的に確認し、必要に応じて修正を行ないます。具体的な数値が提示されることで、改善点をより明確に捉えることができます。
また、統計データの活用は、同じ研修を繰り返す際の改善指標にもなります。この結果を元に次回の研修企画へ反映させることで、研修の質が向上します。統計データの活用は、研修の有効性を検証し、持続的な改善を進めるために重要なステップです。
自由回答の分析方法
自由回答式のアンケートでは、参加者の直感的な意見や思考を引き出すことができます。ただし、その分析は手間がかかるため、事前の設計が重要です。
主な方法としては、「内容分析」があります。この手法は、回答の中から一定のテーマやパターンを見つけ出し、カテゴリ分けするものです。例えば、研修の満足度についての自由回答なら、「内容の充実度」「教材の質」「インストラクターの質」などのカテゴリで分類し、それぞれのカテゴリに言及した回答数をカウントします。
また、AIを活用した自然言語処理ツールも有効で、大量の自由回答データから意見の傾向や要望を自動的に抽出できます。ただし、ツールによる分析も人間のチェックが必要です。
どの方法を選ぶ場合も、重要なのは「参加者の声」をよく理解して研修の改善に生かすことです。そのためには、意見のフォローアップが不可欠です。
アンケート結果の可視化
結果の可視化の具体的方法としては、グラフやチャートを使うことで、回答傾向やパターンを一目で把握することです。例えば、質問ごとの回答分布を円グラフや棒グラフで示すことで、どの項目が一番評価が高かったのか、どの項目が改善が求められているのかが視覚的にわかります。
また、ヒートマップを利用すれば、回答者の注目度や興味度を色の濃淡で視覚化できます。これらの可視化手法は、結果を分析し、効果的な改善策を考え出す上で非常に役立ちます。
ただし、情報の見せ方によっては誤った解釈を生む可能性もあるため、結果の解釈は慎重に行う必要があります。
フィードバックと改善策
フィードバックと改善策の段階は、研修アンケートの過程において非常に重要です。これは、次回の研修をより良くするための具体的な手段となるからです。
以下、具体的に解説していきます。
アンケート結果の共有
アンケート結果の共有は、組織内の全員が同じ理解を持つための重要なステップです。共有することで、参加者だけでなく他のスタッフもアンケートの結果から学び、次回の研修に活かすことが可能です。共有方法としては、全体会議やメールでの報告、社内SNSなどが考えられます。
一方、結果の詳細を共有する際は匿名性をきちんと保つことが重要です。これにより、開放的な意見交換が可能となり、組織全体の改善に繋がります。
結果に基づいた改善策の策定と活用
アンケート結果をもとにした改善策の作成は研修の質を高める重要な手段です。一方、改善策の活用によって、その企業が持続的に成長し発展していくことが可能となります。したがって、アンケート結果から導き出された改善策を適切に実行し、それを次回研修に反映させることが求められます。
改善策の具体例としては、参加者の理解度が低かったトピックについて研修内容を見直す、または教材を改良する等が考えられます。また、参加者の反応に応じて研修方法自体を設計し直すという選択もあります。
これらの改善策は、研修の効果を最大化し、組織の繁栄に貢献することでしょう。
アンケートを効果的に実施して、教育内容を正しく評価&改善
研修を効果的に実施するためには、参加者のフィードバックを正確に収集・分析したうえで次回の研修に活かすことが求められます。
アンケート結果を関係者と共有し、研修内容や運営についての共通理解を深め、改善の方向性を一致させていくことが大切です。具体的な改善策を策定し、次回の研修に反映させることで、研修の内容が洗練され、さらに教育の効果を高めることができます。
改善策が実際にどのような効果を生んだかを次回の研修で確認するためにも、一度限りでなく定期的にアンケートを実施し、結果を比較することも有効です。継続的なフィードバックサイクルを通じて、研修内容がどんどん進化し、参加者のニーズにより一層応えられるものとなります。
力強い戦力として活躍してもらうためにも、研修アンケートを有効活用して、社員教育を充実させていきましょう。
システム開発会社発、IT人材の採用から育成まで!社員研修なら東京ITスクール
東京ITスクールは、IT人材の採用から育成までを包括的に支援する法人向け人材育成・紹介サービスです。
システム開発事業に長年携わってきた私たちならではの、現場で即戦力として活躍できる確かなプログラムをご提供します。
- IT人材の採用から育成までをトータルで支援
- 新人~管理職まで、階層別の学びをご用意
- 実践豊富なカリキュラムで現場即戦力を育成
おすすめの研修・講座はこちら

東京ITスクール 鈴原
講師としての登壇・研修運営の両面で社員教育の現場で15年以上携わる。企業のスタートアップにおける教育プログラムの企画・実施を専門とし、特にリーダーシップ育成、コミュニケーションスキルの向上に力を入れている。趣味は筋トレと映画鑑賞。