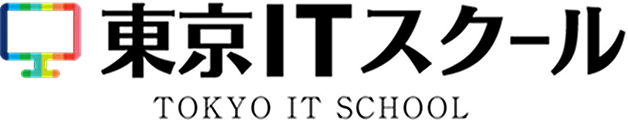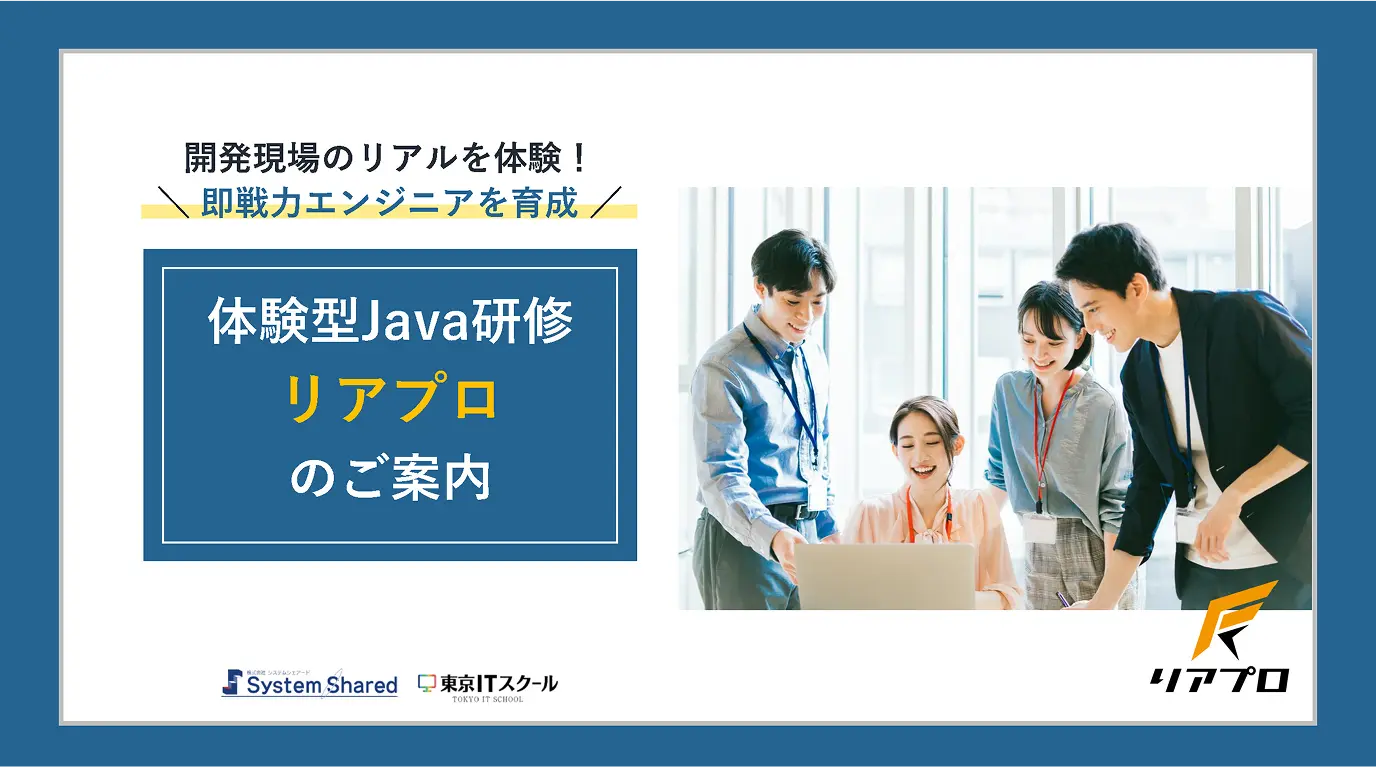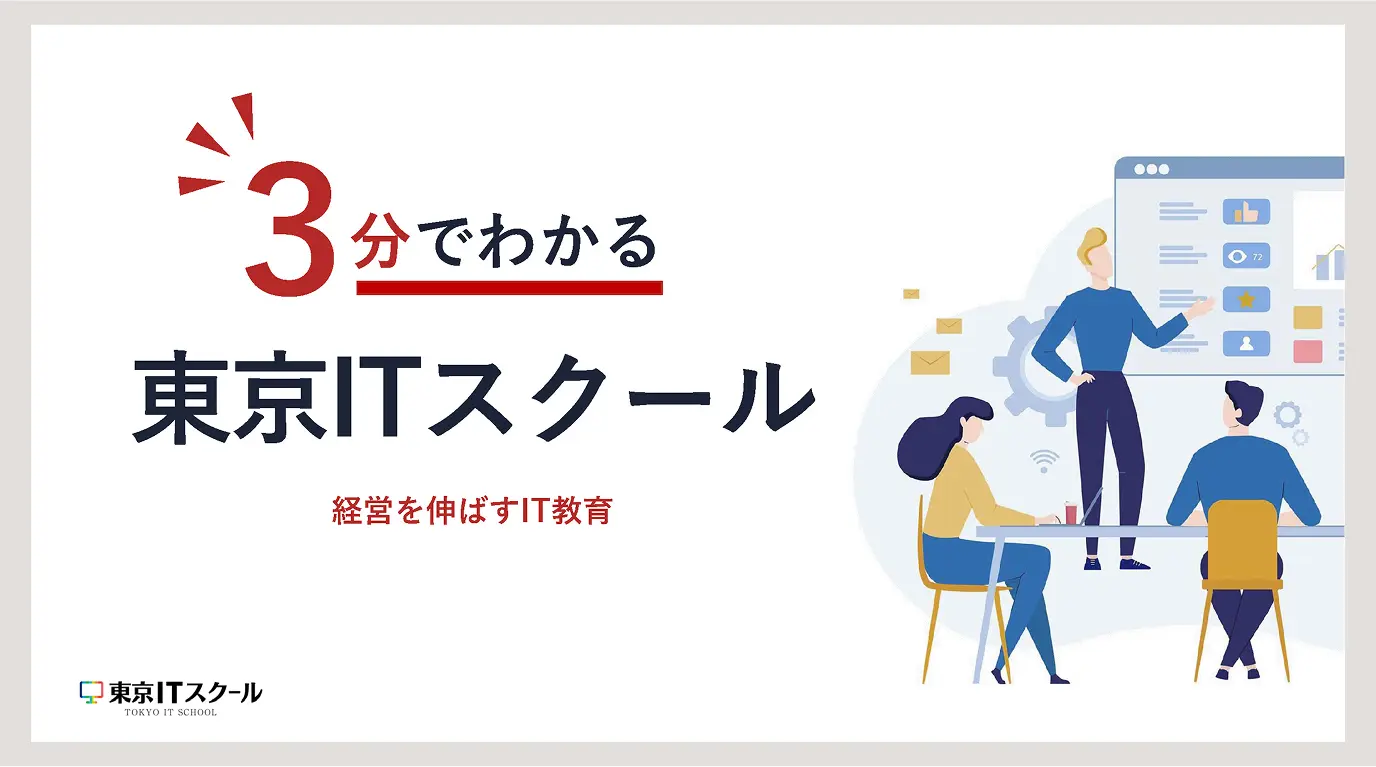【セクシャルハラスメント研修資料】成功の秘訣と利用できる資料まとめ

企業の社内外に対する高いコンプライアンスが求められる現在、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど各種ハラスメントは絶対にあってはならないことです。研修を行う企業も多くありますが、資料をどのように用意したらよいかわからないという声も少なくありません。
この記事では、セクシャルハラスメント研修の資料についてまとめます。以下の点について具体的に解説していきます。
- セクシャルハラスメントとは何か
- 利用できる資料とツール
- 企業文化とハラスメント防止
企業の担当者の方は参考にしてみてください。
セクシャルハラスメントとは何か
まず、セクシャルハラスメントとは何か確認しましょう。以下の点から解説します。
- 法規制と企業の責任
- 具体的な事例と対策
- ハラスメント防止のためのポリシー
- 効果的な研修プログラムの設計
- 内部通報制度の重要性
順に見ていきましょう。
法規制と企業の責任
セクシャルハラスメントに関する法規制は労働基準法や男女雇用機会均等法などに定められており、企業がこれらを遵守しなければならないことは明確です。
特に男女雇用機会均等法では、ハラスメント対策を含む円滑な人事施策の実施が求められています。企業の責任としては、具体的な行動規範や内部通報制度の設立、そしてそれらの適切な運用が期待されます。
企業の責任は従業員の安全を確保することだけでなくハラスメントが生じない文化を醸成し持続することにあります。
具体的な事例と対策
セクシャルハラスメントの具体的な事例としてよくあるものに、性的な言動が含まれる冗談やジョーク、性的な描写のある映像や写真の無理な視聴強要、明らかに恋愛感情を前提としないキスやハグなどの身体接触などがあります。これらは全て、被害者が不快と感じた場合、ハラスメントとなります。
対策としては、まず企業として明確なガイドラインを設け、それを全従業員に周知することが重要です。また教育研修を定期的に実施し問題の本質と重大性を理解させることも必要です。具体的には、ハラスメントが及ぼすマイナス影響の説明、法的な罰則と企業の処分規定の説明、具体的な事例を示してハラスメント行為の判断方法を教えるなどがあります。
内部通報制度も重要な対策の一つです。従業員が不適切な行為を経験または目撃した場合に、安心してその事実を報告できる環境を作り上げることが必要となります。具体的には、通報窓口を複数設ける、匿名での通報を可能にする、報告者のプライバシーを尊重し報復行為を禁止するなどが求められます。
ハラスメント防止のためのポリシー
ハラスメント防止のためのポリシーは企業の職場環境を守る重要な役割を果たします。まず明確な定義と範囲を設けることで、従業員が具体的に何がハラスメントにあたるか理解しやすくなります。またハラスメントが発生した際の対応手順や通報の手段とその保護を明確にすることで、被害者が相談しやすい環境の整備が可能です。
これらの取り組みは従業員が安心して働ける環境を作り、結果として生産性の向上にも寄与します。企業のハラスメント対策は法令遵守だけでなく組織の健全な成長を支える重要な要素となるのです。
効果的な研修プログラムの設計
効果的な研修プログラムを設計するためには、具体的なセクシャルハラスメントの事例を提示してそれに対する適切な対応を参加者自身に考えさせることが重要です。
またハラスメントが起こった場合の報告手順や相談窓口についても明確に伝えるべきです。そして研修は一方的な講義だけでなく、グループディスカッションやロールプレイなどのインタラクティブな方法を取り入れると、理解が深まります。さらに企業のリーダー層が積極的に参加し一貫したメッセージを発信することで組織全体のハラスメント防止への意識向上を図ることができます。
なお、研修が一度きりのものでなく継続的に行われることで、問題意識の維持と改善への取り組みが期待できます。
内部通報制度の重要性
セクシャルハラスメントの問題を適切に管掌するためには、内部通報制度が重要な役割を果たします。この制度により被害者や目撃者は自身の声を安心して企業に伝えられます。この流れが確立することで、企業は問題の早期発見や速やかな対応が可能となります。また社員が通報しやすい環境を整えることでハラスメントが隠蔽される事態を防ぎます。
一方で、内部通報制度を設けるだけでは足りません。機能させるためには、匿名性の確保、通報者への報復防止、適切な対応を行う体制の構築が必須です。具体的には通報内容を厳正に処理し、必要であれば外部の専門家を巻き込むなどして公正な調査を行うことが求められます。こういった一連の流れは、信頼性の高い内部通報制度を構築するための重要なステップとなります。
利用できる資料とツール
次に、利用できる資料とツールについて解説します。以下の物が挙げられます。
- 厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
- 厚生労働省「職場でのハラスメントの防止に向けて」
- 厚生労働省 あかるい職場応援団「動画で学ぶハラスメント」
- 厚生労働省「みんなでNOハラスメント オンライン研修講座」
- 厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラスメント防止に向けて」
- 厚生労働省「妊娠・出産に関するハラスメントの防止に向けて」
いずれも厚生労働省のサイトからダウンロードできたり、YouTubeチャンネルで視聴することができたりします。
では、順に見ていきましょう。
厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」
URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181888.pdf
厚生労働省が提供する「職場におけるハラスメント対策マニュアル」は、企業がハラスメント防止に取り組むための一助となる信頼性の高いPDF資料です。
マニュアルは明瞭な定義付けから始まり、セクシャルハラスメントの具体例を通じて具体的な認識を深めます。また法的義務や企業が採るべき対策も詳しく説明されています。
これらの情報は、ハラスメントを予防・解決する為のポリシー策定や研修プログラムの設計に活用できます。さらにこのマニュアルは具体的な事例に基づくアドバイスを提供しどのように対応すべきか具体的な手引きを示しています。これにより企業は事例を基にした具体的な対策を立てやすくなります。
厚生労働省「職場でのハラスメントの防止に向けて」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000474783.pdf
厚生労働省が発行している「職場でのハラスメントの防止に向けて」は、企業がハラスメントを防止するための実効性ある方策を示したPDFの資料です。社内研修用の資料として利用できます。
具体的には、ハラスメントの定義と特徴を明確にし事例に基づく対策とその重要性を解説しています。また経営者や管理者の役割を明示しハラスメント防止のための組織風土づくりの重要性を指摘しています。
これらの提言は、具体的かつ実践的で、各企業が自社の状況に合わせて取り組むことが可能です。ハラスメント対策は法律で義務付けられているだけでなく良い職場環境を保つためにも極めて重要です。
この資料は、今すぐ手に入れて、対策の一助にすることをお勧めします。
厚生労働省 あかるい職場応援団「動画で学ぶハラスメント」
URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/
厚生労働省のあかるい職場応援団が提供する「動画で学ぶハラスメント」は、ビジュアルと音声による直感的な理解を促進するための教材です。セクハラだけではありませんが、多数の動画が用意されています。
具体的なハラスメントの事例を描いた動画は、実際に起きえる状況を視覚的に示すことで具体的な対策の取りやすさを向上させます。たとえば社内研修の一部として活用することで従業員がハラスメントの具体的な形を理解し自身の行動を見直すきっかけを提供することが可能です。
また視覚的な教材は言葉だけでは伝えきれない微妙な表情や雰囲気を伝えられるため、ハラスメントが如何に深刻な問題であるかを理解するのに役立ちます。社内のハラスメント防止対策に、ぜひ活用してみてください。
厚生労働省「みんなでNOハラスメント オンライン研修講座」
URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/learning/
厚生労働省が提供する「みんなでNOハラスメント オンライン研修講座」は、企業内のハラスメント防止教育を強化するための貴重なリソースです。専門の講師のセミナーを動画化してあります。
パワハラに関する内容ですが、ハラスメントははっきり切り分けられず混在した形で起こることがよくあるため、参考になる内容です。この教育プログラムを活用することで、従業員一人ひとりが具体的なハラスメント事例を理解しそれらを防ぐための対策を学ぶことができます。
またこのオンライン研修は無料で利用でき、時間や場所を問わずアクセスが可能な点が特徴です。従業員の教育スケジュールに柔軟に組み入れることができ、労働者向け、人事・労務の方向けそれぞれ別のカリキュラムが用意されています。企業文化の改革や従業員の意識向上を目指す企業にとって、このような手厚い支援は大変有効です。
厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラスメント防止に向けて」
URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/9-6
厚生労働省が提供する「職場におけるセクシャルハラスメント防止に向けて」は、企業がハラスメントを防ぐための具体的な手引きとなる動画です。11分強とコンパクトな時間で以下の内容がまとめられています。
- セクシュアルハラスメント事例紹介
- セクシュアルハラスメントの解説
- セクシュアルハラスメントの発生状況・実態について
- セクシュアルハラスメント防止に関する法令
- セクシュアルハラスメント防止のために講ずべき措置
この資料を活用して、企業は適切な防止策を講じ、従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境を実現することが可能です。
厚生労働省「妊娠・出産に関するハラスメントの防止に向けて」
URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/9-5
厚生労働省が提供している「妊娠・出産に関するハラスメントの防止に向けて」も13分強の動画です。以下の内容となっています。
- ハラスメントに該当する事例・該当しない事例の紹介
- 妊娠・出産等に関するハラスメントの解説
- 妊娠・出産等に関するハラスメントの発生状況・実態について
- 妊娠・出産等に関するハラスメント防止に関する法令
- 妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために講ずべき措置
いわゆる「マタハラ」に関する動画なのでセクハラそのものについてではありませんが、役立つ内容となっています。
企業文化とハラスメント防止
最後に、企業文化とハラスメント防止についてです。以下の側面からまとめます。
- ダイバーシティとインクルージョン
- マネジメントの役割
- 従業員の意識向上策
- コミュニケーションの向上
- 社内アンケートの実施
順に見ていきましょう。
ダイバーシティとインクルージョン
ダイバーシティとインクルージョンは、ハラスメント防止に重要な視点です。
ダイバーシティは、性別や年齢、人種、国籍、性格、スキルセットなど、社員たちが持つ多様性を認識し尊重することを意味します。インクルージョンは、その多様性を活かし全ての社員が参加し貢献できる環境を作ることです。
ダイバーシティとインクルージョンの考え方を持つ企業は、個々の従業員がお互いの違いを理解し尊重する風土を作ることができます。これは、ハラスメント防止にも繋がるのです。
マネジメントの役割
マネジメントの役割はハラスメント防止において極めて重要です。彼らは組織のルールを作り、それを徹底する責任があります。
具体的にはハラスメント防止ポリシーの策定・実施、研修の計画・運用、そして対応の適時性と適切性を確保する役割があります。またリーダー自身がモデルとなり、ハラスメントを許さない姿勢を示すことで社員の意識も向上します。
マネジメントがリーダーシップを発揮し尊重と公平性のある職場環境を育むことでセクシャルハラスメントの防止に大きく貢献できます。
従業員の意識向上策
従業員の意識向上策は、ハラスメント防止にとって鍵となる要素です。まず始めに、各従業員がセクシャルハラスメントとは何か、法的な規制や企業の責任、具体的な事例と対策を理解することが重要です。次に定期的な研修を通じて、従業員がハラスメント防止のためのポリシーや研修プログラムに対する理解を深め、自身の言動を見直すことが求められます。
一方で、従業員がハラスメントをなくすための行動を起こすためには、具体的な行動指南や、正しい知識の提供だけでなくそれを支える企業文化の存在も必要となります。たとえばダイバーシティやインクルージョン重視の企業文化は従業員全員が尊重され、多様性が認められる環境を作り出すことでハラスメントを未然に防ぐ効果があります。
そして何より、ハラスメント防止のためには、従業員一人ひとりが日々意識を持ち続け、自分自身の言動を見直し必要に応じて改善することが絶対に必要です。そのためにも、企業は従業員の意識向上策について継続的に取り組んでいくべきです。
コミュニケーションの向上
コミュニケーションの向上はハラスメント防止に不可欠です。良好なコミュニケーションは、互いの理解を深め、誤解を招く可能性を減らします。たとえば定期的なミーティングを設けて意見を共有したり、相互理解を促進するトレーニングを行ったりすることが推奨されます。
また従業員間の信頼関係を築くためには、オープンで正直なコミュニケーションが必要です。企業は、職場でのコミュニケーションスキルを向上させるための研修を提供することを考慮すべきです。
社内アンケートの実施
社内アンケートの実施は、ハラスメント問題の具体的な認識を把握し適切な対策を立てるための重要な手段です。全員が匿名で回答できるアンケートを定期的に行うことで従業員が感じている不満や困難、改善が必要な環境等を探り出すことが可能です。また迅速なフィードバック機能を設けることで具体的な問題が浮き彫りになりやすく、早期の解決が見込めます。
ハラスメント予防にも東京ITスクールの研修を
セクシャルハラスメントの予防には、研修による教育が不可欠です。
東京ITスクールでも、リーダー・役職者向けのハラスメント研修をご用意しています。セクハラ、パワハラを生まない職場作りをすることができる内容となっています。ご質問やご興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
おすすめの研修・講座はこちら

東京ITスクール 鈴原
講師としての登壇・研修運営の両面で社員教育の現場で15年以上携わる。企業のスタートアップにおける教育プログラムの企画・実施を専門とし、特にリーダーシップ育成、コミュニケーションスキルの向上に力を入れている。趣味は筋トレと映画鑑賞。