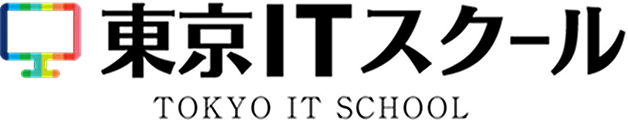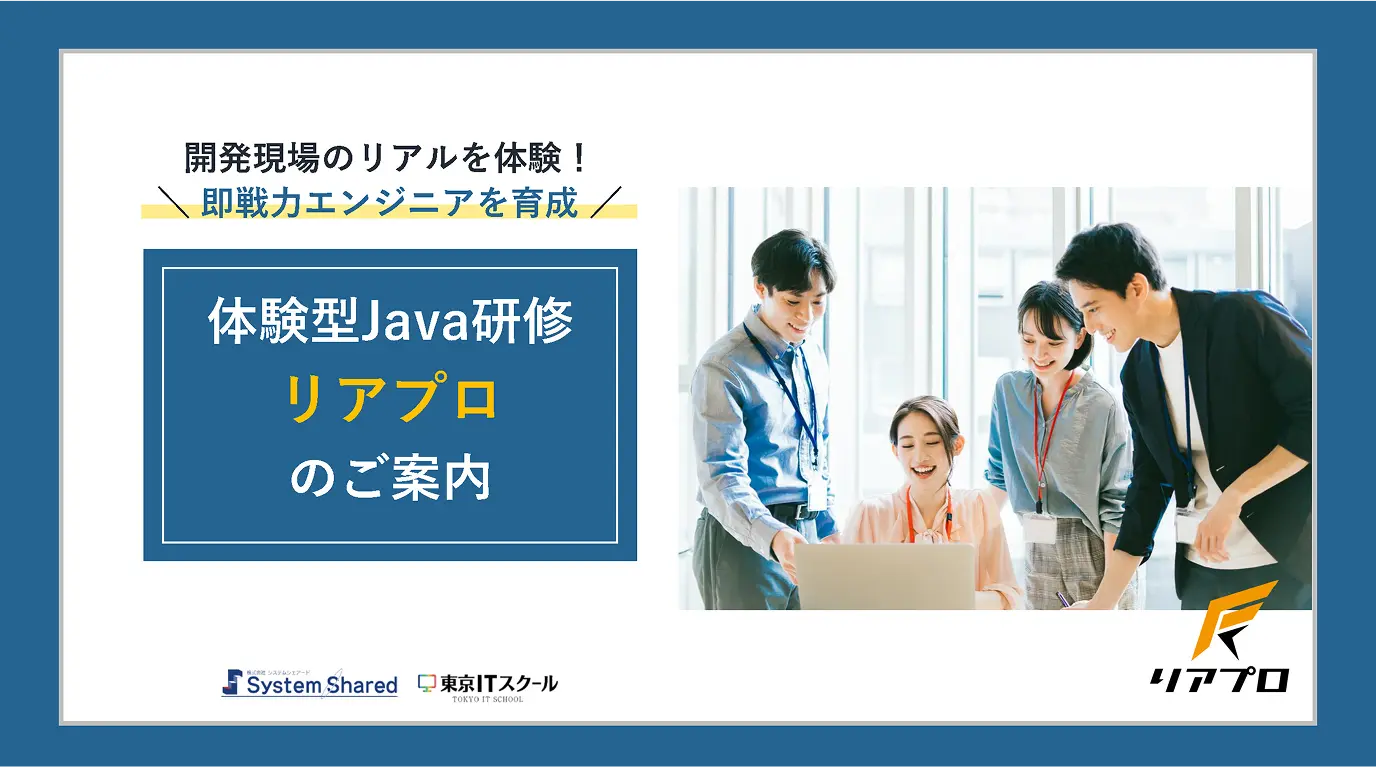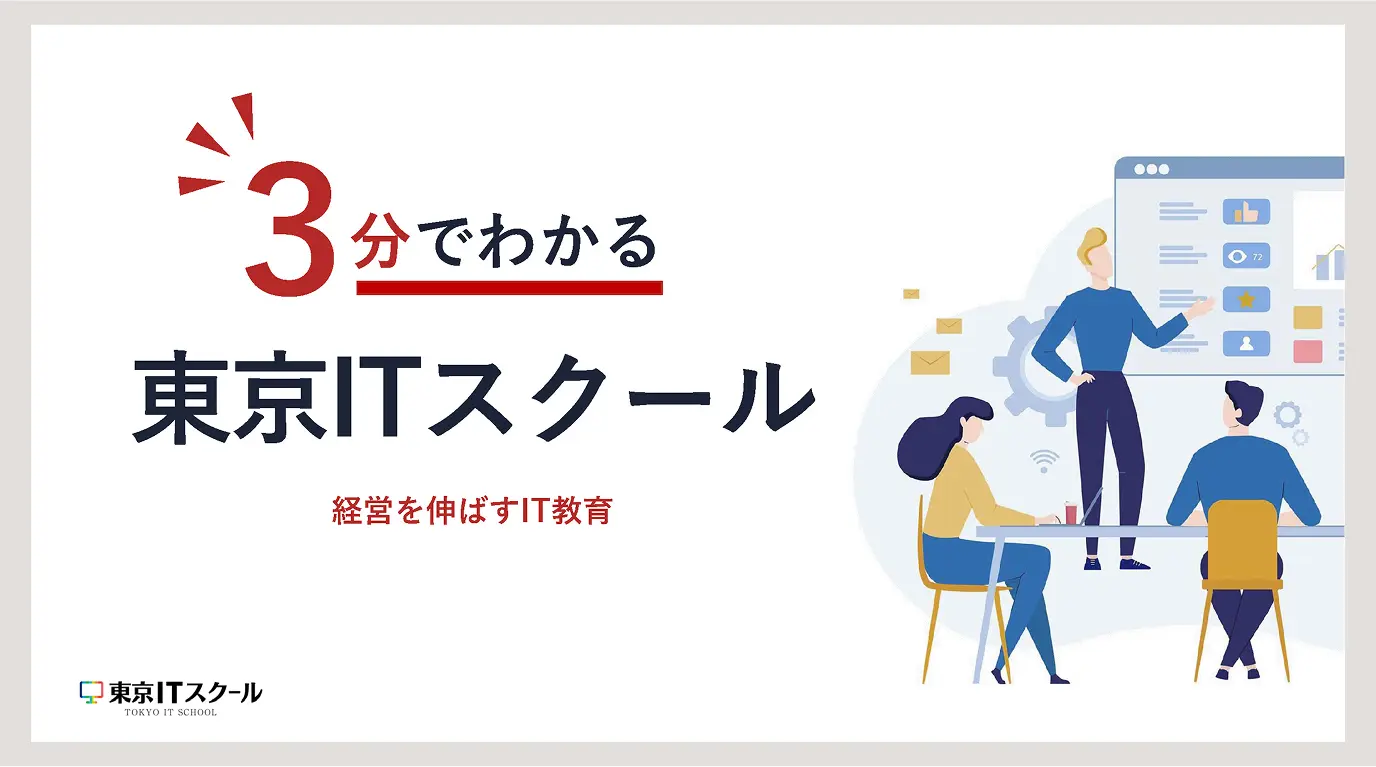研修で起こりがちな課題とは?解決のための方法を解説

効果的な研修を行うためには、起こりがちだったり想定できたりする課題を解決することが大切です。この記事では、研修で起こりがちな課題とその解決方法についてまとめます。この記事を読むことで、以下の理解が深まるでしょう。
- 研修で起こりがちな課題
- 理解度に関する課題解決の方法
- 時間に関する課題解決の方法
- 技術に関する課題解決の方法
- モチベーションに関する課題解決の方法
研修の担当者の方はぜひご一読ください。
研修で起こりがちな課題
まず、研修で起こりがちな課題について解説します。以下のように場合分けしてまとめます。
- 理解度のばらつき
- 時間の不足
- 技術の急速な変化に対応できない
- モチベーションの維持が困難
順に見ていきましょう。
理解度のばらつき
研修における一大課題が理解度のばらつきです。一つのカリキュラム、一つの講師による研修内容が全員に等しく理解されるわけではありません。
これは参加者の個々の学習スタイルや知識水準、経験などによるものです。これを無視して一律の教授を行うと、理解度が高い者は退屈し、逆に理解度が低い者は置き去りにされる可能性が高まります。
時間の不足
研修の過程において、時間の不足は常に挑戦となります。特に技術の研修は内容が複雑で、一定の時間をかけて理解・実践する必要があります。しかし、参加者は日常的な業務に追われ、研修に十分な時間を割けない場合も多いです。
新人研修などでも、必ずしも時間に余裕があるとは限りません。不測の事態が発生したり、思ったほど理解されず時間をかける必要が生じたりするなど、時間が不足することは頻繁に起こります。
技術の急速な変化に対応できない
技術の急速な変化に対応することも研修の大きな課題です。
とくにIT業界は日進月歩で進化を続けており、昨年習ったテクノロジーがすでに古いものになり、新しく学ばなければならない状況が常にあります。これは研修の内容も同様で、新たな技術やツールが出てきたときには迅速にそれを取り入れて、研修カリキュラムを更新する必要があります。
しかし、それは研修を提供する側にとっては大きな負担となります。また受講者側もその変化に追いつくことが困難で、結果としてスキルの格差が生じてしまうという問題も生じます。
一方で、こうした変化の速さに対応することが、企業が競争力を維持するためには必要不可欠です。企業はその変化の速さを把握し、それに対応するよう研修をプランニングする必要があると言えるでしょう。
モチベーションの維持が困難
研修参加者のモチベーション維持は容易なことではありません。長期間にわたる研修は新たな知識を吸収しながらも、日々の業務をこなすという二重の負荷を伴い、参加者のエネルギーと集中力を消耗します。
さらに個々の研修内容が参加者のキャリア形成に直接つながるわけではない場合、その意義や価値を理解しにくいことでモチベーションの維持が困難になります。
理解度に関する課題解決の方法
ここからは上記の課題それぞれについて解決方法を解説していきます。初めは理解度に関する課題解決の方法です。以下の方法があります。
- 質の高い研修資料の提供
- 小グループでのディスカッション
- ペアプログラミング
1つずつ確認していきましょう。
質の高い研修資料の提供
理解度に関する課題を解決するための一つの方法として、質の高い研修資料の提供が挙げられます。研修資料とは、参加者が研修内容を理解し自己学習を進めるための重要なツールです。特にIT領域では専門知識と技術が求められるため、理論説明から具体的な操作方法、例題まで網羅的に押さえた研修資料が不可欠です。
また研修資料は研修後も資料として活用可能で、自習の際にも役立つ点も重要な要素の一つです。
小グループでのディスカッション
理解度のばらつきへの対策として、小グループでのディスカッションは非常に有効です。一人ひとりが発言する時間が増え、直接的なコミュニケーションを通じて理解を深めることができます。また参加者間のアイデア共有や異なる視点からの問題解決が可能となり、全体の理解度が均一化されます。
この手法を取り入れることで個々の理解度の差が埋められ、チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。
ペアプログラミング
ペアプログラミングは、エンジニア研修の現場で非常に効果的な学習法の一つです。2人1組で一つの問題に取り組むことで、互いのスキルや理解度のギャップを埋めることが可能となります。また相手のコードを見ることで新たな発見があり、自身の技術力を高めることもできます。事実、実際の仕事の現場ではチームでの開発が多く見られます。
そのため、ペアプログラミングは現場での協働体験を提供するという点でも有効です。具体的には、互いにアイデアを出し合い、タスクの分配、問題解決のための議論などを通じて、チームでの作業を経験することができます。
時間に関する課題解決の方法
次に時間に関する課題解決の方法です。以下の方法が挙げられます。
- 効率的なスケジュール計画
- 短時間での集中講義
- 自習時間の確保
1つずつ見ていきましょう。
効率的なスケジュール計画
スケジュールについて、多くの企業では全ての参加者が必要な知識と技術を習得できるように各セッションの時間割を事前に定めています。これは分散学習の概念に基づいています。情報は短い時間に集中して学ぶよりも、数日または数週間にわたって少しずつ学ぶ方が効果的に記憶に定着するという理論です。
一日の研修時間を細かく区切り、講義、実習、休憩、フィードバックのセッションをバランス良く配分することで、参加者の疲労を軽減し、学習効果を最大化します。更には、研修の進行状況に応じてスケジュールを柔軟に調整することも求められます。
これにより、急遽必要となった追加のトピックを取り入れることも可能になります。
短時間での集中講義
短時間での集中講義も解決手段の一つとなります。一般的に、人間の集中力は長時間続けると途切れがちになります。よって、長時間にわたる研修よりも短い時間内でダイレクトに必要な知識を学ぶ形式が効果的です。
具体的には、1回の講義を30分~1時間程度に設定し、その間に特定のテーマを徹底的に学ぶというものです。これにより受講者は短時間で集中して学び、理解度を深めることが可能となります。また一つのテーマに絞って学ぶことで、無駄な情報の混在を避け必要な知識へのアクセスをより効率的に行うことができます。
しかし、集中講義のモデルを活用する際は講義内容の密度が濃くなるため、受講者の理解度を確認するための適切なフィードバックシステムを併せて設けることが重要です。この配慮を忘れずに行えば、短時間での集中講義は非常に効果的な学習方法となります。
自習時間の確保
自習時間の確保は、研修の成果を最大化するための重要な鍵となります。自身のペースで学ぶことで理解度を深めることが可能となり、疑問点をクリアにするための時間となります。また教えられるだけでなく、自ら学び探求する力も同時に鍛えられます。
企業においては、定期的な自習時間を設けることや、研修後も自習が続けられるような環境や教材を提供することが求められます。
技術に関する課題解決の方法
次に、技術に関する課題解決の方法です。以下の方法があります。
- 最新の技術動向に対応した研修内容
- 定期的なカリキュラムの更新
- 業界の専門家による特別講義
順に見ていきましょう。
最新の技術動向に対応した研修内容
最新の技術動向に対応した研修内容は、技術に関する課題を解決する上で重要です。例えばAIやビッグデータなどこれからの時代に求められるスキルを研修内容に取り入れることで、参加者が現在進行形のテクノロジーを習得する機会を提供します。
このように最新の技術トレンドを反映した研修プログラムを設計することで、参加者は自身のスキルを市場価値の高いものに変えることが可能となります。
具体的にはクラウドやAIなど最先端の技術を研修の一部に取り入れ、社員のスキル向上を図っている事例があります。これにより、研修受講者は常に最新の知識を学ぶことができ、自身のキャリアパスにも積極的に働きかけることができます。
定期的なカリキュラムの更新
定期的なカリキュラムの更新は、最新の技術に対応した研修を提供するために不可欠です。カリキュラムを定期的に見直し最新の技術の情報を取り入れることで、学習者が新しい知識を身につけることが可能になります。
しかしカリキュラムの更新だけでなく、それを実行する教員のスキルも重要です。教員が最新の情報を把握し、それを的確に学習者に伝える能力は、成功する研修には欠かせません。この点では研修の外注化が効率よい解決方法だと言えるでしょう。
業界の専門家による特別講義
業界の専門家による特別講義は、技術の急速な変化への対応策の1つです。これは新たな視点を提供し、新技術を理解し適用するための具体的な手引きを提供します。
さらに専門家から直接学ぶことで、その分野での最新のトレンドや革新的なアプローチについて深く理解することができます。研修生は現場で即座に活用できる最先端の知識とスキルを修得できます。
モチベーションに関する課題解決の方法
最後に、モチベーションに関する課題解決の方法についてまとめます。以下の方法があります。
- 具体的なキャリアパスの提示
- 成果物の公開とフィードバック
- ゲーム化要素の導入
1つずつ見ていきます。
具体的なキャリアパスの提示
具体的なキャリアパスの提示は、研修生のモチベーション維持に有効な手法の一つです。具体的な成長イメージを描くことで目標への明確なビジョンを持つことが可能となり、その達成に向けて積極的に学習に取り組む意欲が生まれます。
キャリアパスの提示は、社員の自己成長を促進するだけでなく組織全体のスキルアップにも寄与します。
成果物の公開とフィードバック
成果物の公開とフィードバックの活用は、学習者のモチベーション向上やスキルの向上に大いに寄与します。
具体的には、自分の成果物を公開することで他の人からのフィードバックを得ることができ、自己評価だけでなく他者評価を通じた学習と改善が可能となります。また他の学習者の成果物を見ることで、さまざまな視点やアイデアを吸収することもできます。
プロジェクトの中で成果物を作り、公開し、フィードバックを得ることで、学習者の成長を促すことができます。しかしこの取り組みを成功させるためには、公開やフィードバックの文化を育てることが不可欠です。それには組織全体での理解と協力が必要です。
ゲーム化要素の導入
ゲーム化要素を研修に取り入れることで、参加者のモチベーションを上げる効果が期待できます。ゲーム化とは、スコアやバッジ、リーダーボードなどのゲームから取り入れた要素を使い、実世界の行動や業務を楽しげに進める手法です。
特に長期間に渡る研修や自己学習のモチベーション維持に有効で、多くの大手企業も採用しています。根本的な学びの姿勢や自己肯定感を高めることで、長期的な成果を生み出す土壌を作ります。またゲーム化研修では他の参加者との競争や協力プレイによる繋がりが生まれ、コミュニケーションの活性化にも寄与します。
研修のゲーム化は、新たな学びのスタイルを提供して楽しみながら継続的にスキルを身につけるための効果的な方策と言えるでしょう。
東京ITスクールの研修を活用しよう
自社の研修の課題解決に限界を感じている場合は、ぜひ東京ITスクールの研修をご利用ください。外部のサービスを利用することは最短の解決方法で、東京ITスクールではさまざまな内容の研修を用意しています。
ブラッシュアップを繰り返し今もなお改善を続けているため、研修で問題・課題となる多くの点が解決されています。プロフェッショナルの講師による研修で、多くの実績と高い評価を得ています。ご興味やご質問がある方は、お気軽にご連絡ください。
おすすめの研修・講座はこちら

東京ITスクール 鈴原
講師としての登壇・研修運営の両面で社員教育の現場で15年以上携わる。企業のスタートアップにおける教育プログラムの企画・実施を専門とし、特にリーダーシップ育成、コミュニケーションスキルの向上に力を入れている。趣味は筋トレと映画鑑賞。