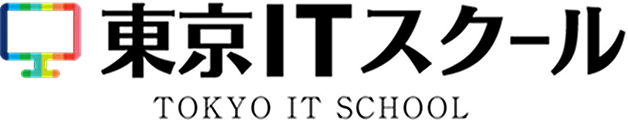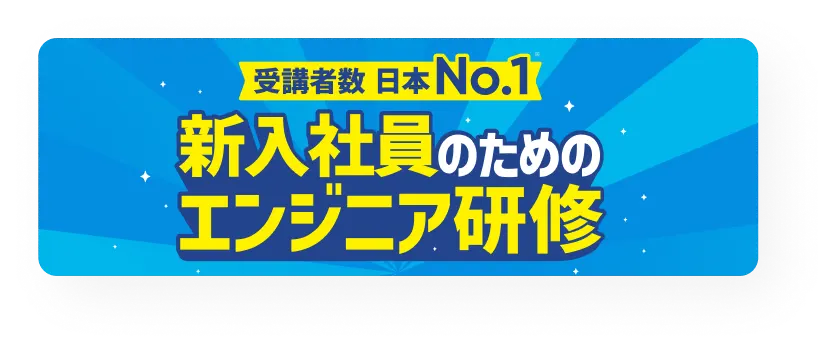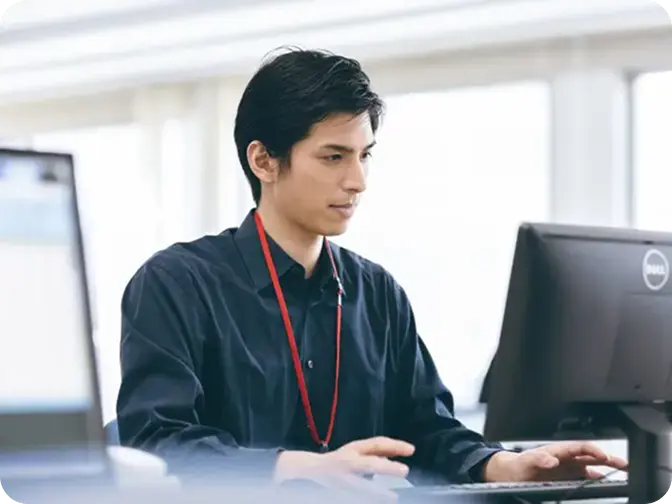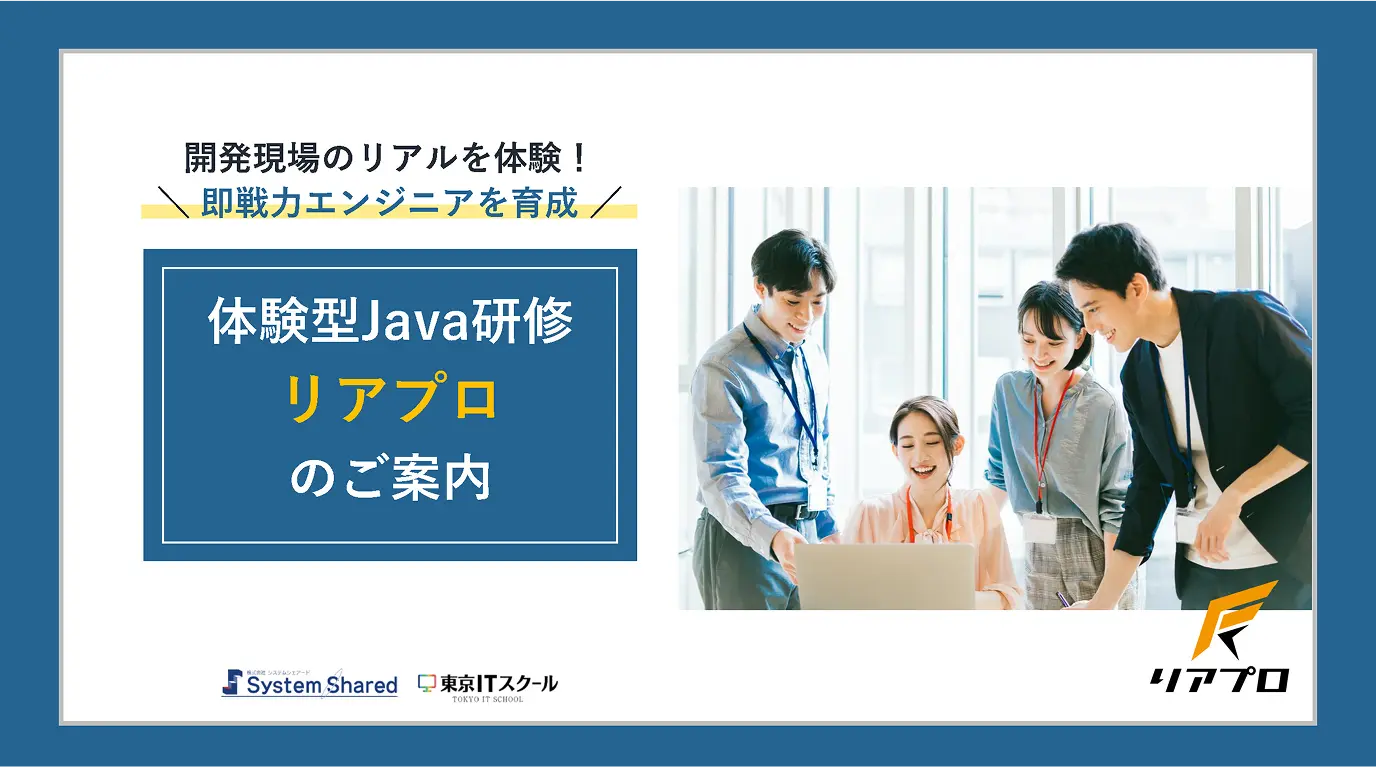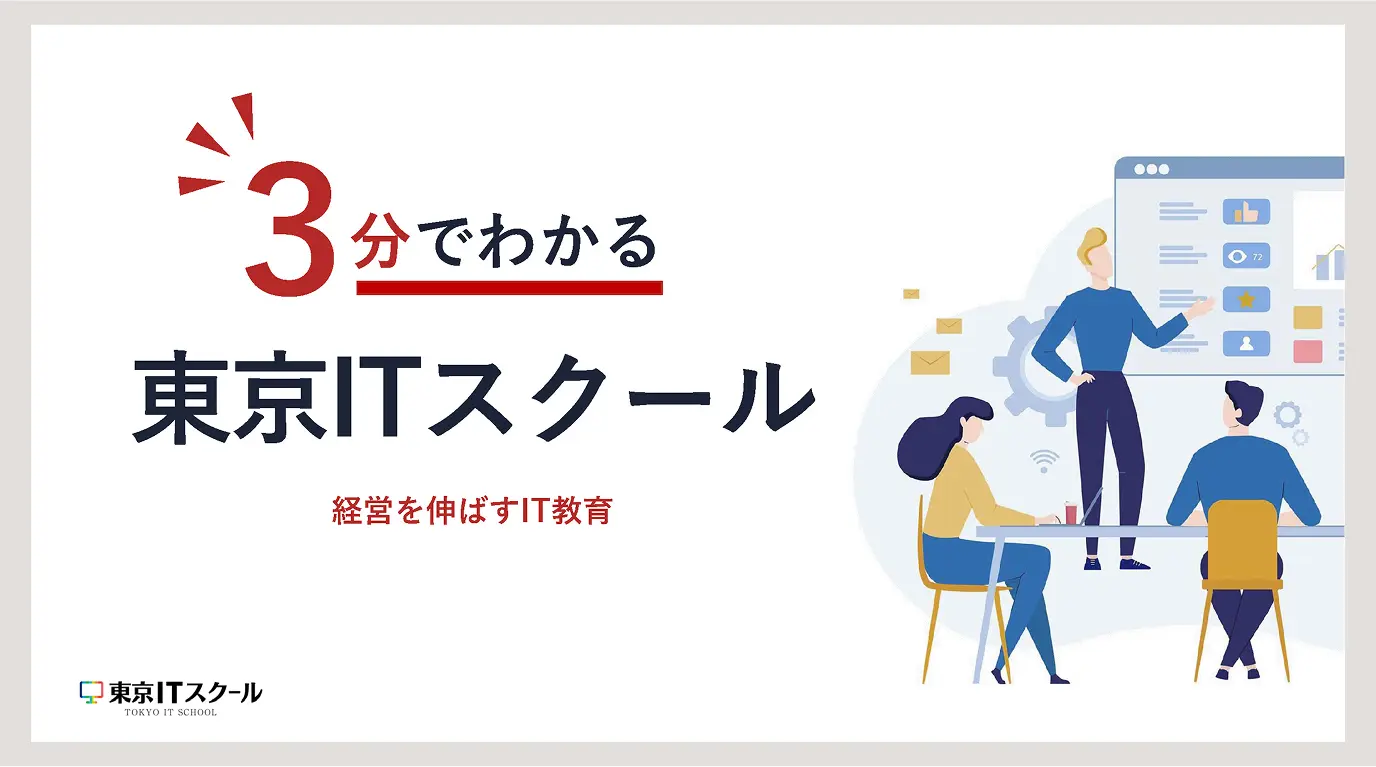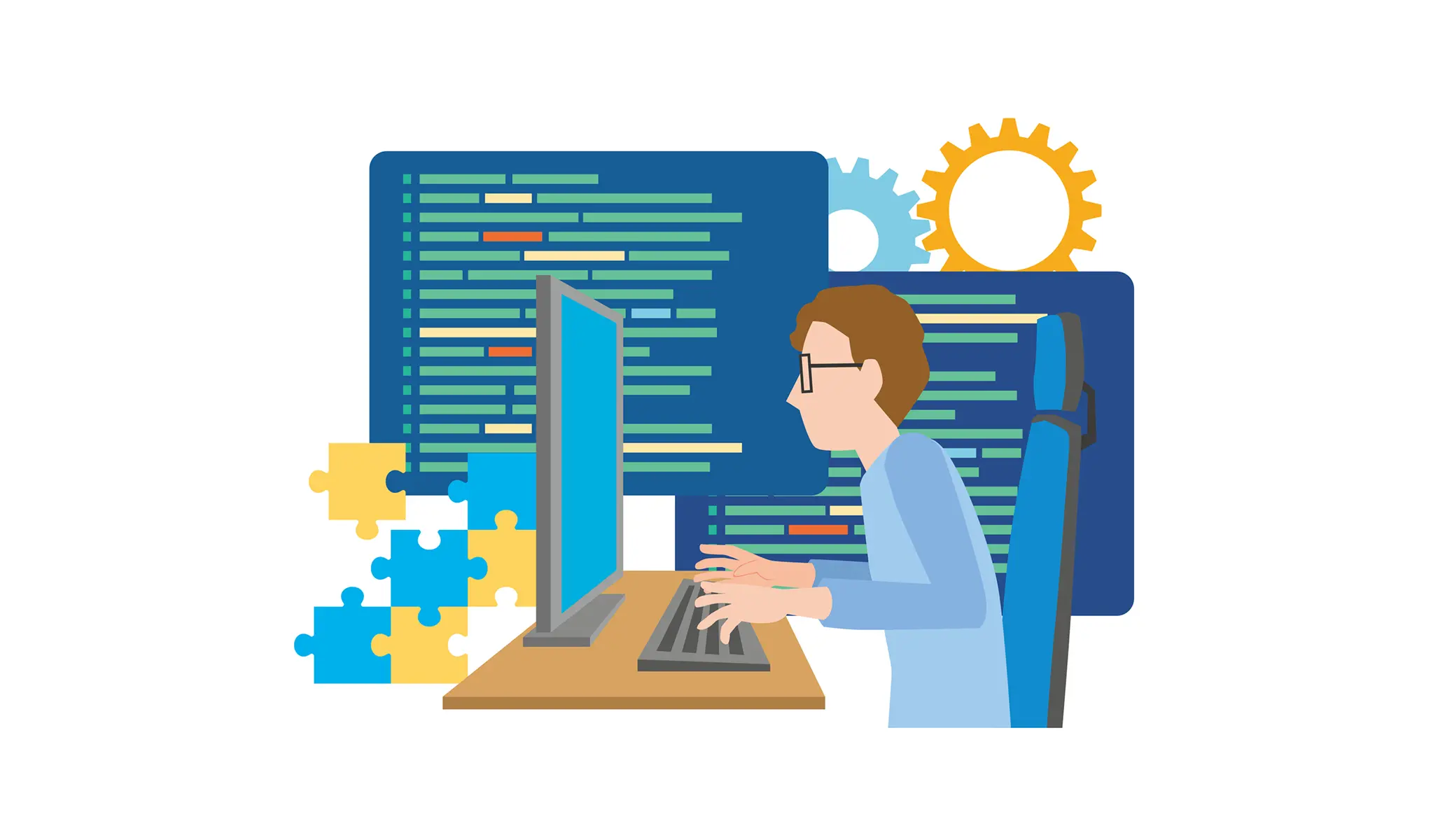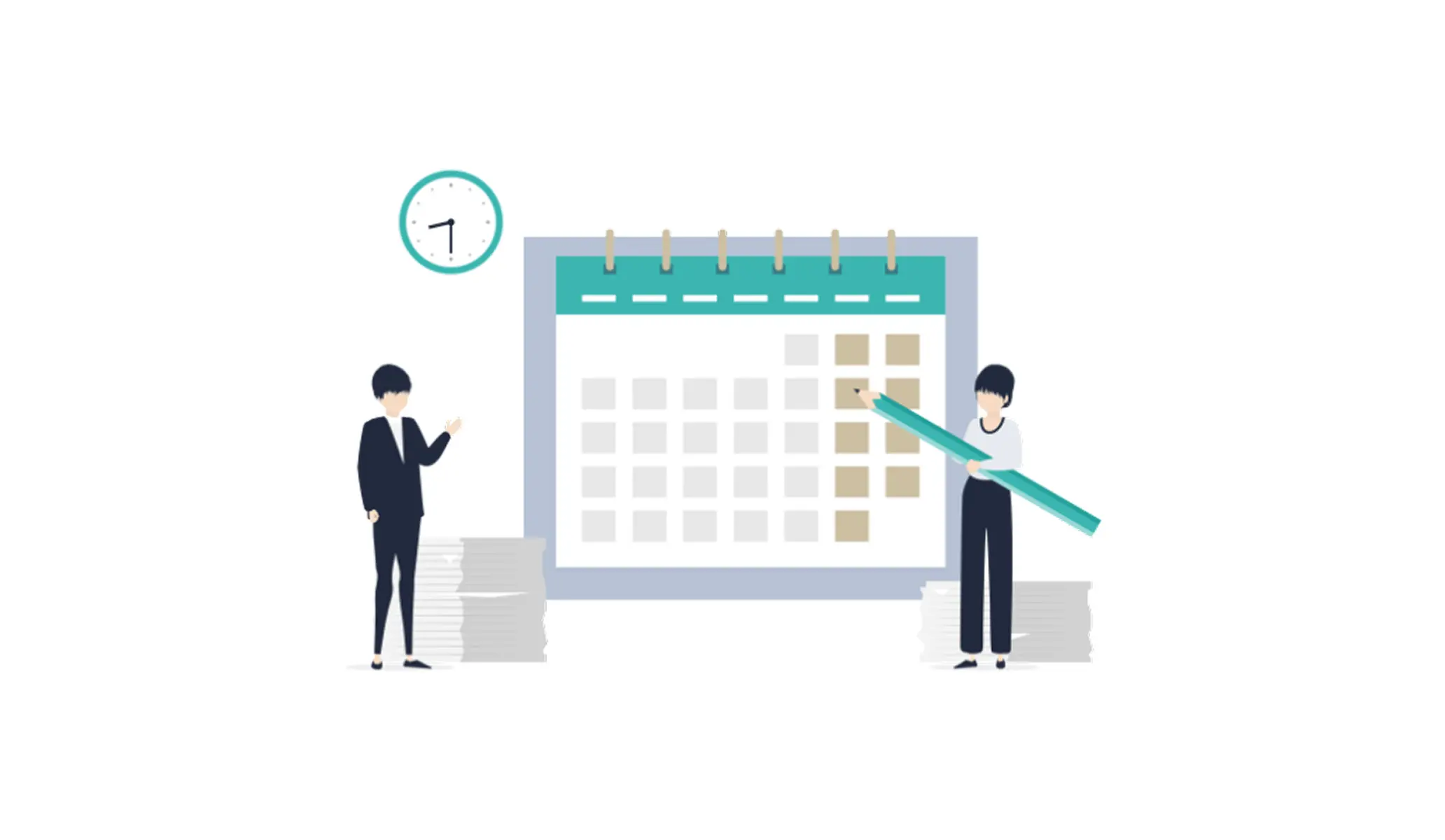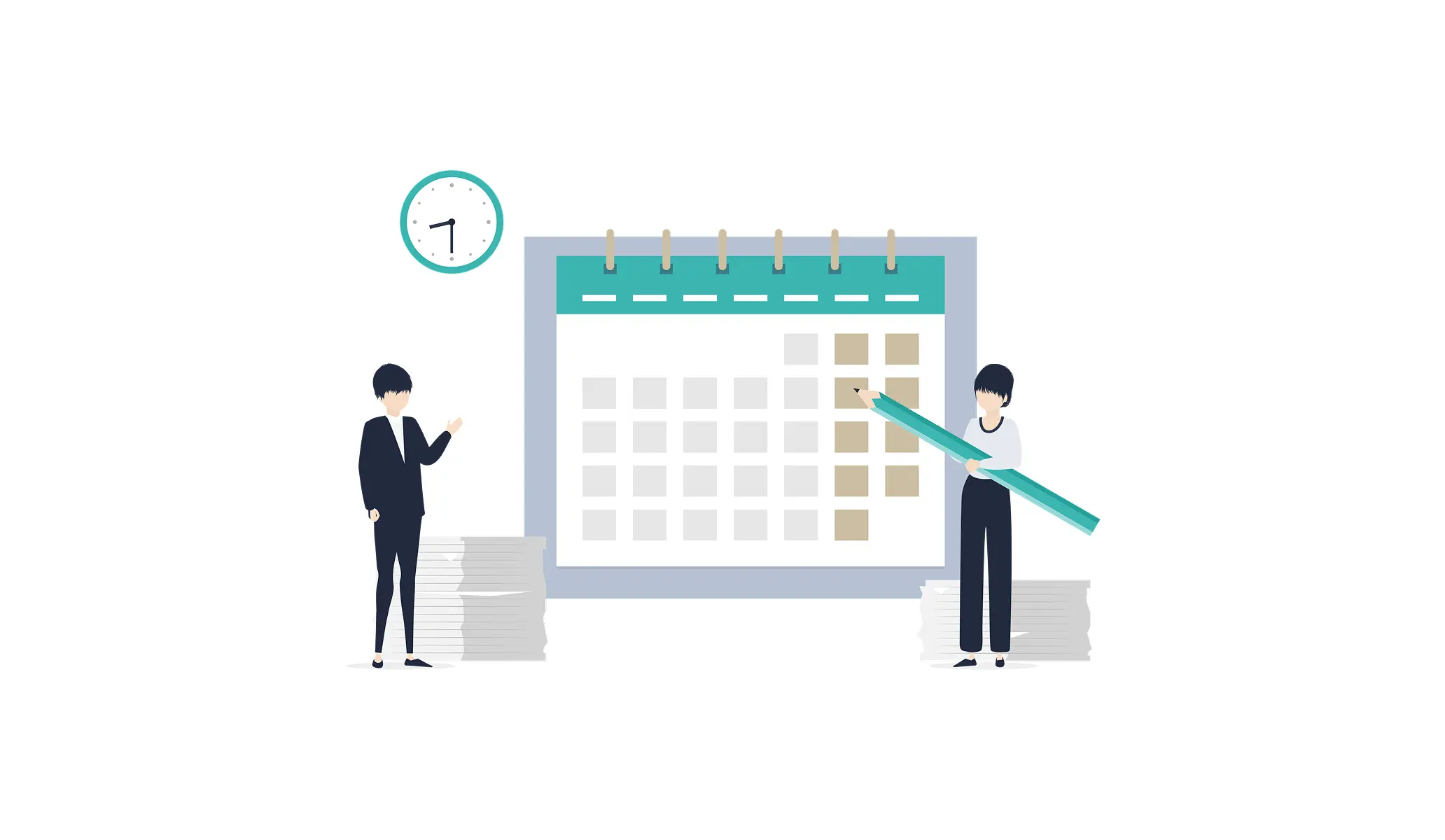7つの習慣とは?要点をまとめてわかりやすく解説!おすすめ研修・書籍も紹介

「最近、退屈な毎日を送っている」
「人として成功したいが、何をすれば良いかわからない」
そのような方におすすめしたいのが、スティーブン・R・コビー博士が提唱する「7つの習慣」です。聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「7つの習慣」は、簡単に言ってしまえば、普遍的な人生哲学です。現在「7つの習慣」に関する様々な本が市販されていますが、要約・まとめ版でもサクッと読んで実践できるものではありません。
そこで本記事では、「7つの習慣」の要点をわかりやすく解説します。学びを助けるおすすめ書籍はもちろん、動画で学べる研修講座もご紹介しますので、今の状況を変えたい・成功をつかみたいと考えている方はぜひ参考にしてください。
「7つの習慣」とは?
「7つの習慣」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
「7つの習慣」は世界中の成功者の間で読まれているベストセラーであり、人生をより良いものにするために必要なメソッドです。まずは、「7つの習慣」の概要を解説します。
人生哲学のベストセラー本
「7つの習慣」は、スティーブン・R・コビー博士が唱える人生哲学を記したベストセラー本です。
「成功者が読んでいるビジネス書」や「自己啓発書」として紹介されることもありますが、どちらも「7つの習慣」を正しくとらえていません。
「7つの習慣」は、よりよい人生を生き、成功をつかむために必要な原理原則・普遍的な哲学です。そのため、読んですぐに実践できるハウツー本とはまったく異なります。「7つの習慣」はシンプルなようでいて奥が深く、書かれていることが骨太のため、人によっては途中で読むのを挫折してしまうことも珍しくありません。
しかし、繰り返し読み、理解を深めることで、現状を抜け出しより良い人生を生きるためのヒントが得られることから、現在まで読み継がれているのです。
「7つの習慣」を学ぶメリット
「7つの習慣」を学ぶと、次のようなメリットが得られます。
- 長期的に良い変化を起こし続けるために必要なことがわかる
- 順番に実践することで人生のステージを変えることができる
- より良い人生を送るために必要なことがわかる
「7つの成功」は、ビジネスで成功を収めるためのノウハウ・テクニックと思われることもありますが、その実態はあくまでもより良い人生を送るために必要な人生哲学です。
コビー博士は、著書の中で「成功を目指すならば、まず成功を支える土台となる人格を構築することが何よりも重要である」と述べています。
「7つの習慣」を通じて、より良い人格を形成するのに必要なエッセンスを学ぶことで、ビジネスでの成功はもちろん、リタイアしてからも続く成功や「より良い人生」が得られるでしょう。
前提として押さえておきたい3つの原則

「7つの習慣」を学ぶにあたって、押さえておきたい前提があります。それは次の3つです。
- 人格主義
- パラダイムシフト
- インサイド・アウト
人格主義
人格主義は、「7つの習慣」を実践するうえで常に心に留めておきたいメソッドの核です。
コビー博士は「成功は、個性、社会的イメージ、態度・行動、スキル、テクニックなどによって、人間関係を円滑にすることから生まれる」とする考え方を個性主義とし、表面的なテクニックに過ぎないと評しました。
一方で、「実りのある人生には、それを支える基本的な原則があり、それらの原則を体得し、自分自身の人格に取り入れ内面化させてはじめて、真の成功、永続的な幸福を得られる」という考え方が人格主義です。
博士は人格主義に基づき、自身をより良い人格に変えていくことこそが、成功への道であると説いています。
つまり、「7つの習慣」は表面的なノウハウ・テクニックを学ぶことではなく、人格主義に基づいて自分の人格や生き方を変えるメソッドなのです。受動的に受け取るだけでなく、自ら「変えよう」という強い意志を持って学ぶことが、「7つの習慣」を学ぶ上で非常に重要になってきます。
パラダイムシフト
パラダイムシフトとは、簡単に言ってしまえば「物事の見方を変える」ことです。
「7つの習慣」を学ぶ上で、物事の見方を変えることは非常に大きな意味を持ちます。
人は、見聞きし触れるものありとあらゆるものに対して無意識にフィルターをかけ、自分が見たいように見ています。そのフィルターを取り払い、別の視点から物事を見ることで気付くことは決して少なくありません。
物事の見方を変えることは、人格にも影響を与えます。たとえば、自分は自身のことを「親切な人間だ」と思っていてもこれはあくまで自分自身の見方であり、他の人はそう思っていないかもしれません。
「7つの習慣」を学ぶにあたっては、どれだけ物事の見方を変えられるか・変えようと行動できるかが重要になってきます。
インサイド・アウト
インサイド・アウトとは、「自分が変わることで、周りも変わる」という考え方です。自分が変わることで、周囲にも良い影響を与えていくことを指します。
人は、現状に不満があると「周りの環境や人が悪い」と思いがちです。しかし、「7つの習慣」においてその考え方は推奨されません。
実践する際は、「成功したい・より良い人生を送りたいなら、まず自分が変わる」というインサイド・アウトの意識を持って行動し、良い影響を波及させていくことが重要になります。
「7つの習慣」の要点を解説
ここからは、「7つの習慣」の要点をわかりやすく解説します。「7つの習慣」を理解する際のヒントにしていただければ幸いです。
第1の習慣 主体的である
「7つの習慣」のうち1つめの習慣は、「主体的である」ことです。主体的であるためには、次の3つのことを心がけましょう。
- 物事に対する反応を自分の意思で決める
- 物事の見方を変え、発する言葉をポジティブなものにする
- 他人がどう思うかではなく、自分がどうするかを意識する
何かショックなことがあったとして、それにどのような反応をするかは、人それぞれです。他人が悲しんでいるから・怒っているから自分も悲しむ・怒るのではなく、自分はどう感じ、それをどう表現するかは自分で決めるようにしましょう。
また、発する言葉をポジティブなものにすることも重要です。
「何もできることはない」と悲観的な言葉ではなく「他の方法を考える」と言い換えたり、「〇〇だったらいいのに」を「自分はこうしよう」と物事の見方を変えてみましょう。
主体的な人生を送るには、他人の欠点や周囲の環境からネガティブな影響を受ける頻度を減らすことも重要です。他人も、周囲の環境も、自分が変えようと思って変えられるものではありません。
自他の境界に線を引き、自分の影響がおよぶ範囲を明確にすることが主体的に生きるカギになります。
物事の見方を変えて主体的に生きられるようになると、次第に良い影響が周囲に波及し始めます。主体的に生きる習慣を身につけることが、「7つの習慣」を実践する際の基礎になるのです。
第2の習慣 終わりを思い描くことから始める
第2の習慣は「終わりを思い描くこと」です。物事ははじまりがあれば必ず終わりがあります。手始めに、自分の葬儀の場面を真剣にイメージしてみましょう。
葬儀の場面をイメージする際は、参列してほしい人や、その人たちにどんな人だったと言ってほしいかを思い浮かべてみてください。
「明るく朗らかな人だった」とか「思いやりにあふれた人だった」といった自分が望む他人からの評価には、自分の中にある本質的な価値観が反映されています。
それらを踏まえて、「そのような評価を得るにはどうすれば良いか」を考えてみてください。自分の終わりをイメージすることで、それに至るためのプロセスが見えてきます。
第3の習慣 最優先事項を優先する
ここまでに身につけたことを実践するには、まず何をすべきかをはっきりさせましょう。
「7つの習慣」の3つめは「最優先事項を優先する」です。
最優先事項を決定すると聞くと、タスクや時間管理を思い浮かべる人は少なくありません。しかし、「7つの習慣」では自分自身の価値観における最優先事項を決定することが重要になります。
人生を充実させるために何が必要かを洗い出し、それを実行するために不要なものを削りましょう。
具体的には、来週の予定を立ててください。
自分の役割(親やマネージャーなど)と達成したい目標を決め、そのための行動計画を立てます。1週間が終わった時点で、自分が大切にしている価値観に沿って行動できたか・価値観と目標に対して誠実であったかを評価してください。
計画の通りに行動できず未消化のタスクがあったとしても、自分の価値観に沿って行動できていたなら良しとしましょう。
第4の習慣 Win-Winを考える
ここからは、自分のことだけでなく、他人との関わりについても目を向けていきましょう。第4の習慣は、自分も相手もWin-Winの関係を作るにはどうしたら良いか考えることです。
人との関わりにおいて、自分も相手も勝つ・利を得るのは容易ではありません。自分だけが利を得ることもあれば、相手だけが利を得ることもあります。なかには、相手のために自分を押し殺してしまうこともあるでしょう。
しかし、それでは豊かさは広がっていきません。
自分も相手も利を得られないなら、時には「やらない」という選択も必要になります。
誰もが豊かになる・利益を得るにはどうすれば良いかを考えることは、自分から周囲に良い影響を波及させていくうえで基本となる考え方です。
第5の習慣 まず理解に徹し、そして理解される
どんな人でも、自分を理解しようとしてくれる人に悪い感情は抱きません。他人と関わるときは、「まず相手を理解する」よう心がけましょう。
相手を理解するには、相手の話に耳を傾ける必要があります。多くの人は、人の話を「次に自分は何を話そうか」と考えながら聞いています。しかしそれでは相手を心から理解することはできません。
相手を理解するためには、自分の経験をひけらかさないことも重要です。人はともすれば、自分の経験をもとに評価やアドバイスをしたくなってしまいます。しかし、相手を理解したいなら、そういった言動は慎むべきです。
相手に対して理解しようという姿勢を示せば、相手もまたあなたを理解しようとしてくれるはずです。
人と関わる際は、まず相手に対して理解をしめす――そうして初めて自分も理解されるということを、第5の習慣は示しています。
第6の習慣 シナジーを創り出す
シナジーというと難しく聞こえますが、シナジーとは「互いの違いを認め合い、互いの弱みをカバーし合う」ことです。
これまでの習慣を実践してきた人であれば、他人と自分の違いを認め合い、他人の弱点や苦手をカバーすることもできるでしょう。
この時重要なのが、互いの違いを認め合うことと、妥協することはイコールではないということです。「仕方ないから〇〇をする」のではなく「より良い方向に進むため第3の案を考える」ことができれば、1+1は10にも100なり得ます。自分と全く違う他人と接することは、物事の見方を変えるにも大きな影響を及ぼすでしょう。
第7の習慣 刃を研ぐ
第7の習慣は、簡単に言うと「自分自身をアップデートし続ける」ということです。
自分の中にある良心に従って自分自身を高め続けていくことでのみ、忍耐力や自制心、意思の力といったものが生まれます。自分が主人公となってより良い人生を送るには、常に自分を磨き、高めていく必要があるのです。
理解を深めるのに役立つ本5選
ここからは、「7つの習慣」の理解を深めるのに役立つ本を5冊ご紹介しましょう。
完訳7つの習慣普及版 人格主義の回復
読みやすく持ち歩きやすい、新書版の書籍です。わかりやすい訳で、「7つの習慣」をより身近に感じていただけます。
まんがでわかる7つの習慣
マンガを通じて「7つの習慣」が学べる1冊です。「7つの習慣」のエッセンスを詰め込んでいるので、初めて「7つの習慣」に触れる方におすすめです。
7つの習慣演習ノート 改訂版
「7つの習慣」を実践する手掛かりになる演習ノートです。自己評価を記録したり、質問に答えたりすることで、自然と「7つの習慣」が身につきます。
7つの習慣デイリー・リフレクションズ
コビー博士の言葉を収録した1冊です。「7つの習慣」を学び実践し、振り返るきっかけとなる珠玉の365語を収録しています。
7つの習慣 入門手帳2023
1年かけて「7つの習慣」を身につけたい方におすすめの1冊です。第3の習慣を実践するのに役立つ「振り返りシート」や「一週間コンパス」が付属しています。
「7つの習慣」を身につけるのにおすすめの研修
より良い人生を送るために役立つ「7つの習慣」ですが、
「本を読んでもいまいちわからない」
「読書が苦手で、1冊読み終えるのが難しい」
「社員全員の共通認識にしたい」
という方もいらっしゃるのではないでしょうか?そのような方には、研修講座をおすすめします。
「7つの習慣」は、研修を通じて身につけることも可能です。しかし、受講できる研修機関は限られており、フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社か、ライセンス契約をしている機関でしか提供されていません。
さまざまな企業が「7つの習慣」研修を提供していますが、特におすすめしたいのが東京ITスクールの実践編!現場エンジニア向け7つの習慣講座です。
7つの習慣を含めたビジネスマインド・プログラミング技術を総合的に学べる新人IT研修
東京ITスクールは日本で初めて新人IT研修に「7つの習慣」研修を導入しました。
現在も新入社員向けJava研修に「7つの習慣研修」を導入するなど、現場のエンジニアが身につけておきたいスキル・知識として、実践しやすい「7つの習慣講座」を提供しています。「7つの習慣」は、自ら働く意義、意味を見出すのにも大いに役立ちます。現状を変えたい・より充実した生き方がしたい方だけでなく、仕事にやりがいを見出したい方にもおすすめの講座です。
「7つの習慣」を身につけて自分の仕事に意味・意義を見出そう!
「7つの習慣は人生哲学である」と聞くと、「難しそう」「自分には不要なものだ」と思う方もいるかもしれません。しかし、「7つの習慣」にはより良い人生を送るためのヒントが詰まっています。
書籍を読んで理解できなかった、実践の途中で挫折してしまった方は、東京ITスクールの「7つの習慣講座」で学び直してみてはいかがでしょうか。
この機会に新しい習慣を身につけ、自分を主人公に、より良い人生に向けて歩みを進めましょう。
おすすめの研修・講座はこちら

東京ITスクール 湯浅
現場SEとして活躍する傍ら、IT研修講師として多数のIT未経験人材の育成に貢献。現在は中小企業を中心としたDX、リスキリングを支援。メンターとして個々の特性に合わせたスキルアップもサポートしている。趣味は温泉と神社仏閣巡り。