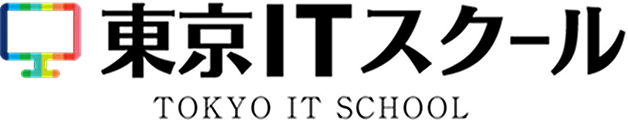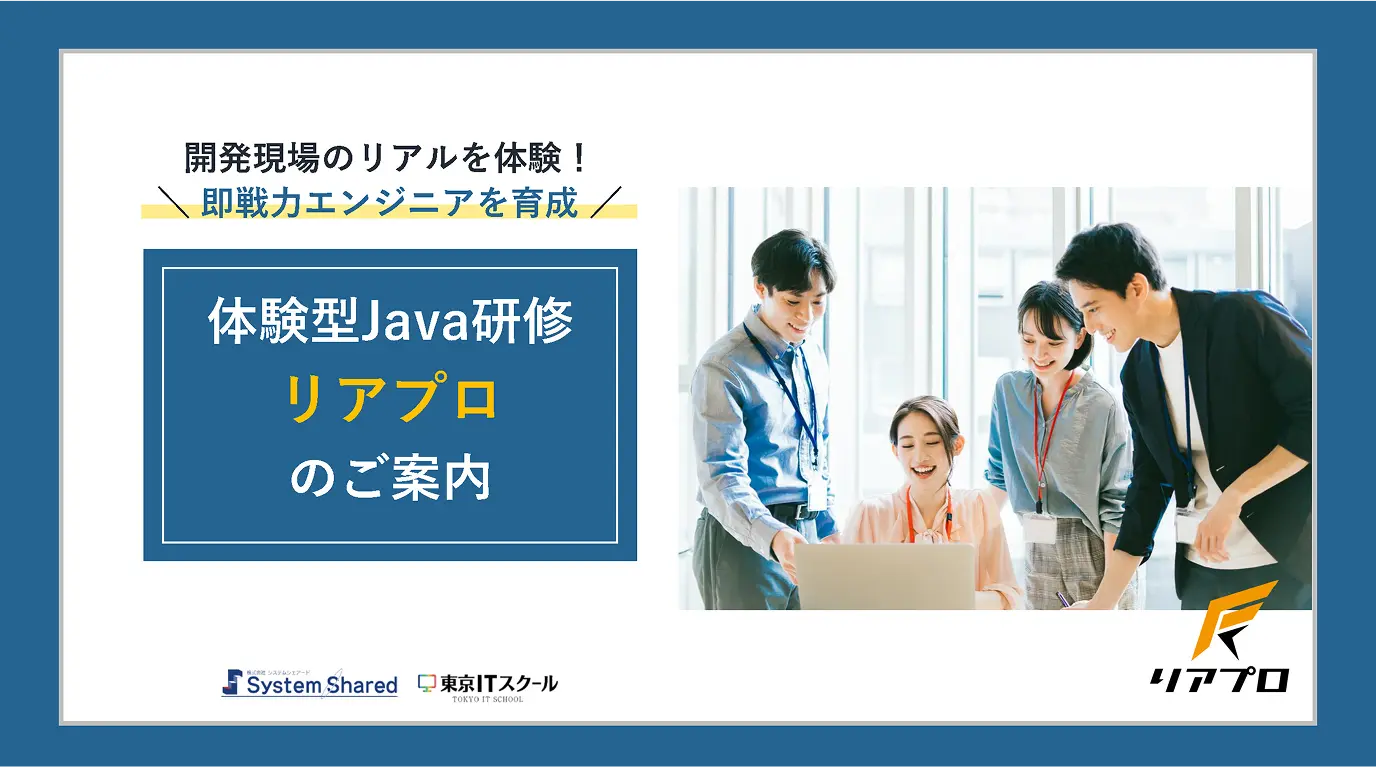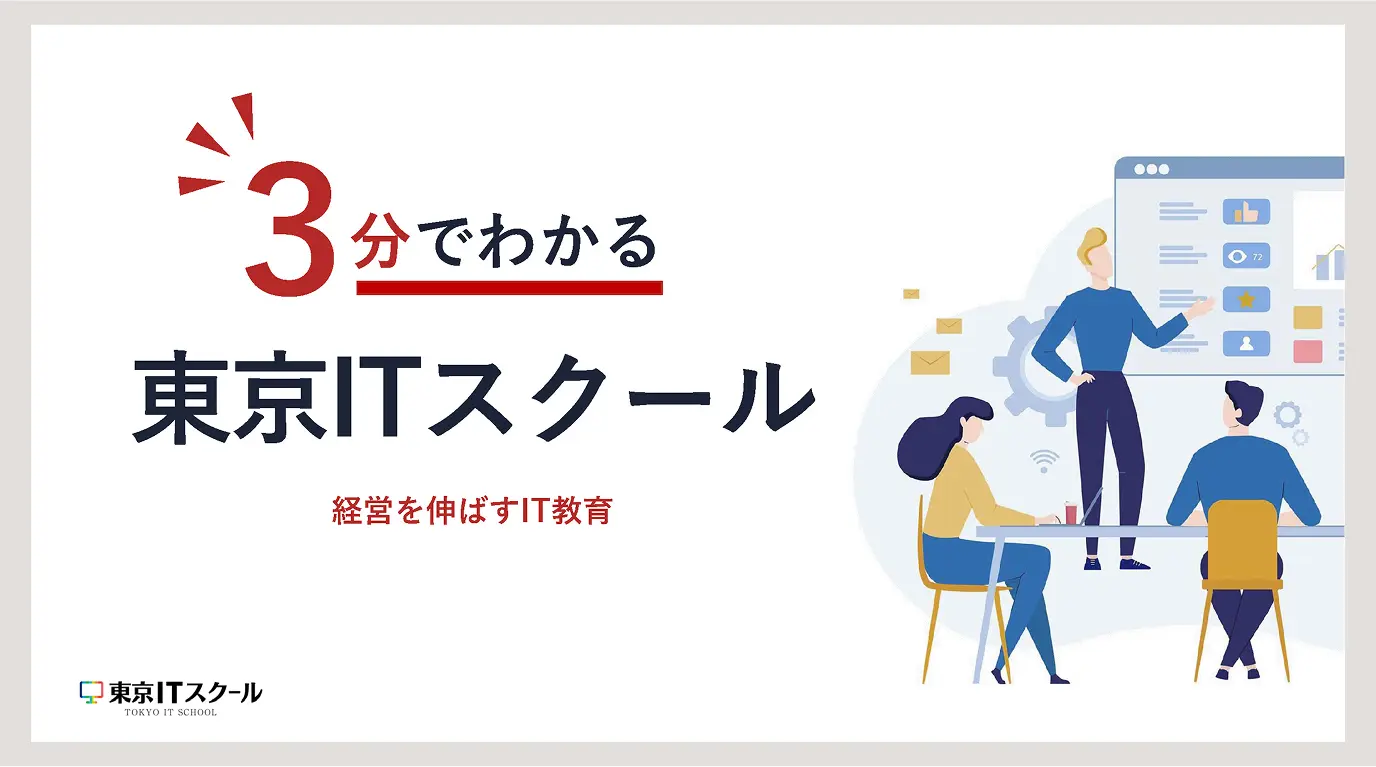リスク管理とは?新任管理職こそ押さえておきたいポイントとプロセスを解説!

管理職の業務は、マネジメントや品質管理など多種多様です。なかでもリスク管理は特に重要な業務とされています。
しかし、リスク管理とはどのようなものか、またどのように行えばよいのかわからない方も多いでしょう。
本記事では、
- リスク管理とは何か
- リスク管理の重要性やリスクの種類
- リスク管理のやり方や行う際のポイント
を解説します。
リスク管理とは

「リスク管理」と聞いても、具体的にどのようなものかイメージできない人も多いでしょう。まずはリスク管理の概要と、リスクヘッジ・リスクアセスメント・クライシスマネジメントとの違いを解説します。
リスク管理とは?
リスク管理とは、企業に影響を及ぼすマイナスの事象(=リスク)の発生を予測して対策を練ることを指します。
リスクは「危機」と直訳されますが、ビジネスにおいては「発生する可能性がある事柄」という意味合いで用いられます。
リスクといっても、様々なものがあります。
たとえば
・情報漏洩
・従業員の人手不足
・株主による訴訟
・賠償責任の発生
・売り上げの減少
・株価や為替相場の変動による損失
・不正アクセスなどのサイバー攻撃
・粉飾決済
・災害による建物や設備の損害
といった事柄は、発生しないに越したことはありません。しかし発生してしまった場合は、適切に対処してできるだけ業務におけるダメージを減らす必要があります。
そこで重要になってくるのが、リスクの予測と回避です。
調査や分析をもとに発生しうるリスクを予測し、回避または必要に応じてリスクを取る選択をすることを「リスク管理」といいます。
リスクヘッジとの違い
リスクヘッジは、リスク管理と違って「予想外の出来事が起きた際の対応・対策を考える」ことを指します。
ビジネスにおける「リスク」の意味は広く、危機のほか「予想どおりにならない可能性」という意味も含んでいます。
どうしても避けられない危機的状況に対して、どうすればダメージを最小限にできるか考えることも「リスクヘッジ」といえるでしょう。
リスクアセスメントとの違い
リスクアセスメントは、調査・分析を通してリスクを特定するプロセスを指します。リスク管理の前段階に位置するものといえるでしょう。
リスクアセスメントは、関係者同士が協力して行うのが一般的です。
クライシスマネジメントとの違い
クライシスマネジメントは、通常の業務では滅多に発生しない事柄への対応を考えることをいいます。
リスク管理が日常業務で発生しうる事柄の予防を目的としていますが、クライシスマネジメントは事件や重大事故、災害といった想定をはるかに超える事柄を対象としているのが違いです。
既存のマニュアルではカバーしきれない事柄が発生した場合、影響やダメージを最小限に抑えるにはどうしたらよいかを考えます。
業務に支障をきたすリスクとは?

ここからは、業務に支障をきたすリスクをみていきましょう。リスクは大きく「純粋リスク」と「投機的リスク」に分けられます。
純粋リスク
純粋リスクとは、企業に損失や損害を与えるだけでプラスの影響が何もないリスクを指します。
発生すればしただけマイナスの影響が大きくなるため、発生そのものを防ぐことが重要です。
純粋リスクには、次のようなものがあります。
・自然災害による設備や建物の損傷
・従業員による資金の横領や着服、窃盗
・売り上げの減少
・コストの増加
・病気や事故による従業員不足
・権利の侵害などによる賠償責任の発生
具体的に、いつ・どのような形で発生するか予測が難しいものです。しかし「損害保険」などを活用することで対策がとれるので、純粋リスクのリスク管理はそこまで難しくありません。
投機的リスク
投機的リスクは損失だけでなく利益を生むこともあるリスクです。「ビジネスリスク」とも呼ばれます。
投機的リスクは企業にとって利益を生むチャンスでもあり、成長のために敢えてリスクを取る企業も増えてきました。
投機的リスクには次のようなものがあります。
・景気の悪化
・為替相場の変動
・政策の大幅な変更
・消費動向の変化
・法律の改正や規制緩和・強化
・新しい技術の開発
投機的リスクは、政治や経済情勢の影響を受けやすく、グローバル化が進んだことでより一層複雑になっています。そのため、リスクを取った際に及ぶマイナスの影響を最小限に抑えるには、関係者が協力して密にリスクアセスメントを行うことが重要です。
リスク管理を行う4ステップ

ここからは、リスク管理のやり方を簡単に解説します。リスク管理の基本は4ステップです。
リスク管理をする際は、以下の4ステップを素早く行うことが重要です。そのためにも、事前に誰が意思決定をするかあらかじめ決めておくようにしましょう。
①リスクを特定する
リスク管理を行うには、リスクを特定する必要があります。
リスクを特定するには、各部門にヒアリングを行ったり、今あるデータをしっかり分析したりすることが重要です。
リスクを特定する際は、主観で「大したことではない」と判断しないようにしましょう。どんなに些細なリスクでも拾い集め、想定されるありとあらゆるリスクを洗い出してください。
②リスクを分析する
リスクには、影響を数字で表せる「定量的リスク」と、数字で表せない「定性的リスク」があります。
定量的リスクを特定する場合は、発生確率とどの程度の影響が出るかを軸にして各リスクをマッピングすると、分析しやすくなります。
数値で表すことが難しい「定性的リスク」を分析する際は、客観的なデータなどを元にできるだけ数字に落とし込むことが重要です。数字に落とし込めない場合は、影響の大・中・小ごとにざっくりと分けるのもよいでしょう。
③リスクを評価する
①でリスクを洗い出すと、思いのほか多くのリスクがあることに驚くかもしれません。すべてのリスクに対応できればよいですが、数が多ければ多いほど難しくなります。
対応するリスクを決めるには、②で行った分析を元にリスクを評価することが重要です。
定量的リスクであれば、マッピングを元にリスクを評価しましょう。基本的には発生頻度が高く、影響も大きいリスクの管理を最優先に行ってください。
リスクのなかには環境や社会情勢の影響を受けるものもあるので、マッピングだけで判断せず、冷静に優先順位をつけることが重要です。
リスクを評価する際は、リスク管理後にどれだけリスクが残るかもあわせて評価しておきましょう。
④リスクに対応する
リスクを評価し、対応の優先順位を決めたら、順位の高い物から対応に当たります。
リスクへの対応は、「コントロール」と「ファイナンシング」の2通りがあります。
リスクコントロールとリスクファイナンシング
リスクコントロールは、文字通りリスクをコントロールする対応です。具体的には
・回避
・損失の防止
・損失の削減
・影響を受ける場所・物の分離・分散
などがリスクコントロールの手法です。
一方、リスクファイナンシングは金銭的に損失を補填する対応です。保険によって損失を補填したり、自社で損失を負担したりすることを指します
時にはリスクをとることも大切
一昔前までは、リスクは発生させないことが大切であり、その影響を最小限にすることが適切とされていました。
しかし、時代は変わり、最近は影響をできる限り減らしたうえでリスクを取る・増加させるのも適切な方法であると捉えられています。
リスクは事業における危機である一方で、成長や利益追求につながることもあります。
より事業を拡大させていきたいなら、必要に応じてリスクを取ることも大切です。
適切なリスク管理を行うために必要なこと

適切なリスク管理を行うためには、次のことを意識しましょう。
PDCAを回し常に改善し続ける
リスク管理を行う際は、PDCAサイクルを回し、常に改善し続けることが重要です。
特に現代はグローバル化やデジタル化が進み、今まで以上にビジネスのスピードが加速しています。そのような状況では、常に新しいリスクの可能性が生み出されているといっても過言ではありません。
リスクの特定や分析、評価を常に最新の状態に保つことは、適切なリスク管理を行う上で非常に重要です。
PDCAサイクルというと業務効率改善のためのフレームワークというイメージが強いですが、元は品質管理のために考案されたサイクルです。常にPDCAサイクルを回し続けることで、リスクの把握と評価を最新に保つことができるでしょう。
トップがリーダーシップを持って進める
リスク管理においては、組織のトップがリーダーシップを持って推し進めていきましょう。
リスク管理を行う場合、どうしても従業員の業務負担は増えます。そのため、リスク管理そのものに消極的な人もいるでしょう。
しかし、そのような人を気にしていては、リスク管理は進みません。ときにはリーダーが積極的に働きかけ、力強く推進することも必要です。
リスクを共有しやすい組織作りを心がける
適切なリスク管理を行うためには、従業員の協力も欠かせません。現場で働く従業員が気付いたリスクを共有しやすい環境を整えましょう。
同時に、従業員の愛社精神を育むことにも力を入れてください。
会社に愛着を持っている人が多い企業とそうでない企業では、愛着を持っていない人が多い企業の方がリスクが発生しやすいことは想像に難くないでしょう。
普段からリスクを共有しやすい環境が整えば、よりリスク管理がしやすくなります。
リスク管理の手法を学ぶなら研修がおすすめ!

リスク管理の書籍なども多数出版されていますが、実際の現場で使える手法を学ぶなら研修を受けるのがおすすめです。
研修を受けるメリット
リスクマネジメント研修を受けると、次のようなメリットがあります。
・プロによる講義が受けられる
・リスク管理について理論的に学べる
・資格取得につながりやすい
・全社で受講することで共通の認識を持ちやすい
研修を受ける場合、それなりに費用は掛かりますが、それを上回るメリットがあります。まずは初めて管理職に就いた方だけでも、研修を受けてリスク管理の基礎を学んでおくとよいでしょう。
おすすめのリスク管理研修
東京ITスクールでは、これまで管理職・役職の経験がない方にもわかりやすいリスク管理講座を開講しています。ぜひスキルアップ・キャリアアップにお役立てください。
リスク管理に役立つ資格

最後に、リスク管理に役立つ資格を紹介しましょう。キャリアアップにも役立つ資格ですので、リスク管理に慣れてきたら挑戦してみるのもおすすめです。
情報処理安全確保支援士
2017年に創設された比較的新しい国家資格です。
情報セキュリティに関する知識・技能を有することを示す資格で、登録者はその情報が一般公開されます。
試験の合格率は約20%と難易度の高い資格ではありますが、情報関連企業におけるリスク管理のスペシャリストとして活躍するなら、取得しておきたい資格です。
CRISC
2010年に創設された国際的なリスク管理の資格です。IT分野のリスク認識・評価ができることを証明します。
資格取得には、実務経験のほか外国語の語学力も求められるため、取得のハードルは少し高めです。
CRM
一般財団法人リスクマネジメント協会が設けた資格の中で最高位の資格です。
各専門分野のリスク試験に合格するだけでなく、エンタープライズ・リスクマネジャー養成講座を修了しないと受験資格が得られません。
GRMI Diploma
世界随一のリスクマネジメント団体「RIMS」とその日本支部にあたる「リスクマネジメント協会」が創設した国際資格です。
現在はCRMを取得した人のみが受験可能で、非常に難易度が高いとされています。
企業危機管理士
一般財団法人 全日本情報学習振興協会が主宰している資格で、リスク管理の基本を学びたい人にぴったりの資格です。
サービスや広報、法務や顧客対応など、ビジネスにおける様々な分野のリスク管理に関する知識が身につきます。
管理職にはリスク管理の知識とスキルが必要不可欠!

初めて管理職に就いた人にとって、リスク管理はとてもハードルが高く、どのようなことをすればよいのかイメージも湧きにくいでしょう。
リスク管理を適切にすることは、事業の成長や拡大にも大きく寄与するので、管理職に就いたらできるだけ早くリスク管理について学ぶことをおすすめします。
システム開発会社発、IT人材の採用から育成まで!社員研修なら東京ITスクール
東京ITスクールは、IT人材の採用から育成までを包括的に支援する法人向け人材育成・紹介サービスです。
システム開発事業に長年携わってきた私たちならではの、現場で即戦力として活躍できる確かなプログラムをご提供します。
• IT人材の採用から育成までをトータルで支援
• 新人~管理職まで、階層別の学びをご用意
• 実践豊富なカリキュラムで現場即戦力を育成
おすすめの研修・講座はこちら
-

~後輩育成のノウハウを知りたいあなたへ~
尊敬される先輩になれる!人材育成のコツ講座(OJT、フィードバック編)■表示元: カテゴリタグ / リーダー研修
[カテゴリ] リーダー研修
[技術]
[対象者] 中堅社員向け -

〜ベテランリーダーに贈る〜
企業理念に繋げるための「フォロワーシップ」講座■表示元: カテゴリタグ / リーダー研修
[カテゴリ] リーダー研修
[技術]
[対象者] ベテラン社員向け, 管理職向け -

ChatGPT×Googleドキュメント
■表示元: 階層対象者タグ / 管理職向け
[カテゴリ] 生成AI
[技術] ChatGPT
[対象者] 新入社員向け, 中堅社員向け, ベテラン社員向け, 管理職向け -

DX推進のためのグローバル・プロジェクトマネジメント研修
■表示元: 階層対象者タグ / 管理職向け
[カテゴリ] プロジェクトマネジメント
[技術]
[対象者] 新入社員向け, 中堅社員向け, ベテラン社員向け, 管理職向け

東京ITスクール 湯浅
現場SEとして活躍する傍ら、IT研修講師として多数のIT未経験人材の育成に貢献。現在は中小企業を中心としたDX、リスキリングを支援。メンターとして個々の特性に合わせたスキルアップもサポートしている。趣味は温泉と神社仏閣巡り。